教育・子育て
せまる入園準備…何から始めればいい?事前に用意するべきものはこれ

そろそろ入園式。親子ともにソワソワする時期ですね。入園の準備が大変だった!という声を聞いて、焦っている方も多いと思います。
直前に準備でバタバタすることがないように、この記事では
・入園準備はいつ何を揃えればいいのか
・物だけではない見落としがちな準備
についてまとめてみました。ぜひ参考にしてくださいね。
■入園準備は入園説明会まで待つのが鉄則!

さっそくモチベーションを下げそうで申し訳ないのですが…基本的にほとんどの準備は、入園説明会まで待ちましょう。
説明会は1月~3月に開催されることが多いです。
待つべきである理由は、園や学年によって指定の物が異なるため、準備したのに使わなかった、もしくは規定のサイズと違うため買い直さなければいけなかった…なんてこともあるからです。
参考までに3例ご紹介しましょう。
私立A保育園・1歳児クラスに入園する場合
- 昼寝用布団*(ボタン不可。チャック式のみ。)
- おむつと着替えを持ち帰るためのエコバック*
- 着替えを上下3セット分とおむつ
- おしりふき
- ビニール袋*
- 雑巾*(手作り)
- ティッシュボックス
- 食事用エプロン*(手作り)
- 外靴
- 通園バッグ(レッスンバッグ)*
など*縦と横の長さ(㎝)が細かく指定
公立B幼稚園・年少クラスに入園する場合
- お弁当箱、お箸、コップ、ランチョンマット、歯ブラシ、それらを入れる巾着袋(週4回給食、週1回お弁当)
- 着替え上下1セット、それを入れる袋(巾着タイプ)
- 手拭きタオル(ループ付き)、ハンカチ、ティッシュ
- 上靴と上靴袋
- 通園バッグや体操服、植木鉢やお道具箱など園で購入するもの
など
公立C保育園・年中クラスに入園する場合
- 昼寝用布団カバー(布団はレンタルのため不要)
- 体操服3着(私服不可)
- パジャマとパジャマ袋(巾着タイプ不可)
- お箸、コップ、お弁当箱(毎日白米を持参)、歯ブラシ、それらを入れる巾着袋
- 手拭きタオル(ループ付き)、ハンカチ、ティッシュ
- 上靴と上靴袋
- 通園用ななめがけバッグ(園指定なし)
- お絵かきセットや工作セットなど、園で購入するもの
など
園だけでなく、学年によっても全然違いますね。入園説明会までは慌てて用意せず、「もし買うことになるなら」という前提で、購入するお店や好きな柄、キャラクターなどを決めておくといいでしょう。
きょうだいが同じ園に通園するママ友がいるなら、聞いてみるのもオススメです。ただし学年によっても準備物が変わるので、注意しましょう。
■どんな園でも用意しておいた方がいいもの

「とは言っても、入園準備が大変と聞くので早く用意しておきたい!」という方に、今から準備できることをご紹介します。
名前書きの時間を減らすアイテム
用意しておくべきアイテムの一つ。それは、名前シールや名前はんこです。
乳児クラスに入園する場合、園によっては毎日おむつを持っていかなければいけません。その一つひとつに名前を書くのは、結構時間がかかるものです。
名前はんこがあればポンと押すだけなので、かなりの時短になります!洋服のタグや靴下などにも使えます。
将来きょうだいやお友達にお下がりを渡したい場合は、名前アイロンシールがオススメです。記名がいらなくなった時点ではがせるので便利ですね。
さらにコップやお箸、のりやハサミなどの小物には、名前シールが必須です。クレヨン一本一本に名前を書くのはかなり時間がかかるので、シールがあるだけで助かりますよ。
学年があがったり小学校に入学したりするタイミングでも長く使えるので、買いすぎる心配もありません。早めに準備しておいてもいいでしょう。
袋物の手作りが苦手なら
上靴袋やお弁当袋など、いわゆる袋物はどの園でも使います。ただし指定の長さが決まっていることもあるので、市販のものでは合わないことも。
もし裁縫が得意でないのなら、指定のサイズがわかるまでの間に、頼める人を探してみてはいかがでしょうか。
今はフリマアプリでも、セミオーダーで仕上げてもらえるサービスがあります。
入園・入学前の時期は忙しくなるため、早めの予約が大事。今のうちにさがしてみましょう。
■準備は物だけじゃない!通園経路や一日のシミュレーションも

入園準備とは、物をそろえるだけではありません。しっかりシミュレーションしてみることも大事なのです。
実際に送迎の時間に通ってみることで、いろいろなことに気づけます。徒歩通園なら交通量が、自転車や車送迎なら小学生の列などがポイントです。危険ポイントがあったり、その時間ならではの渋滞があったりすれば、別の道を選んだ方が良さそうです。
朝のリズムも変わるかもしれません。いきなり早起きするのは難しいので、入園に向けて徐々に生活リズムを整えましょう。
保育園に入園するなら、職場復帰も同時でしょうか。もし入園とほぼ同時に職場復帰するのであれば、通勤方法のシミュレーションも必須です。園と職場が逆方向の場合、ベビーカーや自転車を保育園に置いて電車通勤できる園もあれば、一切の私物も禁止という園もあります。
これによって送迎の時間も大きく変わってくるので、1日の流れをシミュレーションして、実際にそのリズムで動いてみましょう。
もし疑問点があれば(自動車での送迎は可能か、ベビーカーは置いておけるのかなど)、入園説明会までにまとめておくと、当日にまとめて質問できるので安心です。
■かかる費用も計画的に用意したい
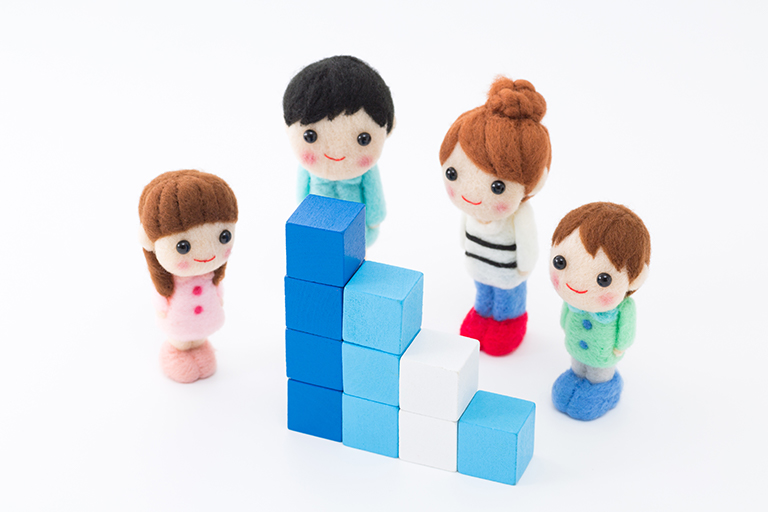
幼稚園や保育園でかかる費用も準備しなければなりません。基本的に、この時期の教育費は毎月の収入でやりくりすることになりますが、意外とかかる費用もあります。
無償化で無料になるもの、ならないもの
2019年10月から、3歳から5歳児の幼保無償化 がはじまりましたね。しかし対象外の費用もあるのです。
- 給食費
- 保護者会費やPTA会費
- 預かり保育や延長保育料
- 制服や植木鉢など園で使う物の購入費
- その他「学級運営費」など園によって実費で徴収されるもの
などがあります。(一例です。年収によってさらなる助成や、自治体によって独自の助成があります。)
ちなみに筆者の通う公立保育園の場合は、絵本無し/延長保育なしで毎月6,000円~8,000円かかりました。延長保育や送迎バスを利用する場合、1万円前後はかかりそうですね。
また私立など指定の制服がある園だと、入園時に3万円~5万円程度 の初期費用がかかることもあります。
教育費の準備方法
無償化の制度がはじまったものの、意外と費用がかかることがわかりました。子供が複数人いればその倍がかかってくる※1ので、結構な出費になります。
※1 自治体によっては、第2子以降は半額や無償化としています。
さらに考えるべき費用は、この時期の保育料・教育費だけではありません。大事なのはこのあと、高校までの教育費 (すべて公立の場合でも平均約540万円※2)、そして大学の費用(国公立大学の4年間平均約537万円※3、私立大学文系の4年間平均約703万円※4)をどのようにして貯めるかです。
※2 文部科学省「平成30年度子供の学習費調査」より。ただしこの中に幼稚園の費用も含まれるため、無償化が始まった今後は少なくなる可能性があります。
※3※4 日本政策金融公庫「令和2年度教育費負担の実態調査結果」より
教育費の準備として、王道と言われるのは学資保険。
しかし今は学資保険の利率が下がり、あまりメリットがないと聞いた方もいるかもしれません。たしかに利率が下がったのは事実ですが、貯め方や保険に対しては「メリット/デメリット」よりも、「合う人/合わない人」で考えるのが正しいです。
なので「教育費をどうやって準備しようかな」に対する答えは、その悩みを持っている人それぞれで異なります。
貯蓄だとつい使ってしまうため、コツコツ貯めたい!と学資保険を選んだ人もいますし、児童手当をジュニアNISAで運用している人もいます。自分なりに選んだ方法であれば、どれも間違いではなく、子供のために教育費を積み立てているといえるでしょう。
ただしどんな方法があるのかわからない、どの方法にどんなリスクがあるのかわからない…そういう状況であれば、今後家計が苦しくなる可能性が高いです。
一度今後の教育費について、夫婦でじっくり話し合ってみましょう。
■入園準備まとめ

保育園や幼稚園の入園準備について、まとめてきました。
- 本格的に準備をはじめるのは、入園説明会が終わってから
- 名前書きアイテムは用意しておく
- 送迎や1日のリズムのシミュレーションも大事な準備
- 教育費の準備方法も夫婦で明確にしておく
入園準備とは、園で使う物(グッズ)の用意だけではありません。毎日の生活リズムが変わるため、スムーズに環境に適応できるよう、あらゆる面で準備しておきたいですね。それと同時に、教育費の準備方法もしっかり考えておきましょう。
※この記事は2020年12月時点の法律・情報にもとづき作成しているため、将来、法律・情報・税制等が変更される可能性があります。
執筆者
ニッセンライフ編集部
ニッセンライフの編集部に所属する、働く双子ママ。
「遊びたい盛り、食べたい盛り、論破したい盛り」の双子を育てながら、
子育て世代の心が軽くなるような情報を発信しています。





