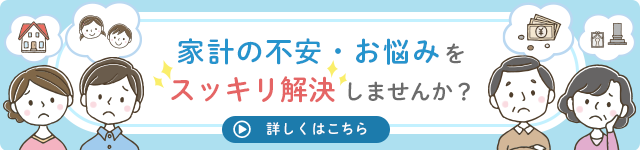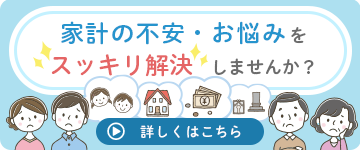家計
【FPが解説】家計簿でクレジットカード払いを賢く付ける簡単なコツ3つ

「クレジットカード払いを家計簿にどう記入すべきか迷ってしまい、家計簿が続かない」
ファイナンシャル・プランナー(FP)として、こうした悩みをよくお聞きします。
たしかに、クレジットカードは利用時と決済時のタイミングが異なるため、真面目に家計管理をしようとする人ほど「どのタイミングで記録するべきか?」と考えすぎてしまい、結果として続けにくくなってしまうことが多いです。
しかし家計簿の本来の目的は、支出の無駄を見つけ、家計をより良く管理することにあります。記録の方法にこだわりすぎず、効率よく支出を把握することが何よりも大切です。
そこで、今回の記事では「クレジットカード払いをどのように家計簿に記録すべきか」を簡単に解説しました。記録の仕方に迷う方や、続かないと感じる方の参考になれば幸いです。
もし、家計簿や支出管理に不安がある場合は、一度FPに相談してみませんか?
日々の家計管理から将来の資産設計まで、あなたにぴったりのアドバイスをご提案します。
今すぐ無料でFPに相談する!
■家計簿でクレジットカード払いを賢く付けるコツ3つ
クレジットカード払いを賢く家計簿に付けるコツは、以下の3つです。
- 支払いのズレは気にしない
- とにかく支出を書き出す
- 費目ごとに予算を決め、無駄遣いを防ぐ
家計簿の本来の役割は、支出の無駄を見つけて家計を見直すことにあります。
要は、家計の見直しができればそれでいいのです。
家計簿の付け方にこだわりすぎる必要はありません。
賢く家計簿を付けて家計を見直すコツについて、わかりやすく解説していきましょう。
コツ①支払いのズレは気にしない
クレジットカードで買い物をすると、その買い物代金の支払いは数か月後です。
そのため、以下どちらのタイミングで家計簿に付ければいいのか、悩む人は少なくありません。
【先に付ける】買い物した時(カード決済時)に家計簿に付ける
【後で付ける】カード明細が届いた時(カード請求時)に家計簿に付ける
結論から言うと、あなたが書きやすい・付けやすい方法ならどちらでもかまいません。
ただ【先に付ける】方法を選ぶと、「カードを使うたびに家計簿に付けるのが面倒」で続かなくなる人が多いと思います。
そこで、ここではクレジットカード払いを【後で付ける】方法を案内します。
後で付ける方法の具体例は、以下のとおり。
【家計簿を後で付ける方法:具体例】
- 12月1日~31日:現金で使った金額を家計簿に付ける
- 12月中旬:10月~11月ごろに利用したカードの利用明細が届く→過去の利用明細を12月の家計簿に付けていく
<家計簿の具体例>
| 使った日付 | 種別 | 費目 | 使った金額 |
|---|---|---|---|
| 12月1日 | 現金 | 食費(スーパーで買いだし) | 8,000円 |
| 12月7日 | 現金 | 日用品費(ドラッグストア) | 5,000円 |
| 12月15日 | カード払い | 光熱費(10月-11月利用分) | 10,000円 |
| 12月15日 | カード払い | スマホ代(10月利用分) | 8,000円 |
| 12月15日 | カード払い | 洋服代(11月利用分) | 10,000円 |
つまり過去の利用明細を、「今月使ったもの」として家計簿に付けていくイメージです。
付ける方法は紙でもスマホアプリでも、続けやすい方法なら何でもかまいません。
「この方法だとタイミングがズレるので、収支が合わなくなるのでは」
そう思うかもしれません。
しかしタイミングのズレより、収支の整合性より、何より大切なのは支出を把握することです。
家計簿は会社の帳簿とは違い、個人の家計をより良くするために付けるもの。
多少ズレがあっても誰も文句は言いませんし、正確に付けるからといって貯蓄が増えるわけではありません。
自分が毎月、何にどれだけお金を使っているのか。
支出の傾向を把握することに、神経を集中させましょう。
方法②とにかく支出を書き出す

家計簿を始めてから数か月間は、とにかく支出を書き出してください。
収支の整合性や支払いタイミングのズレは、一旦脇においておきましょう。
何にいくら使っているのか、支出の傾向を把握することが最優先です。
ある程度書き出していけば、どの費目にお金がかかっているのか、お金の使い方の傾向が見えてくるでしょう。
支出を家計簿に書き出す・付ける方法で代表的なものは以下の3つです。
- 紙の家計簿に書く
- パソコンのExcel・スプレッドシートなどで家計簿を付ける
- スマホの家計簿アプリを使う
自分に合った方法であれば、何を利用してもかまいません。
日記や手帳などを付けていて普段から紙に書くのが好きな人は、昔ながらの紙の家計簿を利用しましょう。
もし仕事をリモートでしていてパソコン環境が整っている人は、Excelやスプレッドシートで自作する方法もあります。
「紙もパソコンも苦手」という場合には、スマホの家計簿アプリがオススメです。
家計簿アプリならクレジットカード会社と連携して、自動でカード払いの支出を付けられる機能があります。カードの他にも銀行や各種キャッシュレス決済とも連携できるため、「細かく付けるのが苦手」な人でも家計簿を続けやすいでしょう。
どの方法を使う場合でも、大切なのは自分に合っているかどうかです。
いくつか試してみて、無理せず続けられる方法を見つけてみてください。
方法③費目ごとに予算を決め、無駄遣いを防ぐ
家計簿に数か月分の支出を付けていくと、どの費目で支出が多いのか、支出の全体像がはっきりしてきます。
そうすれば
「毎月の食費は3万円~4万円くらいかかっているな」
「洋服代はだいたい月5,000円だな」
という具合に、自分や家族のお金の使い方が見えてくるでしょう。
支出の傾向を把握したら、次は費目ごとに予算を設定します。
このとき大切なのは、以下の2つ。
- 毎月の収入から貯蓄額を差し引いた残りのお金で「毎月使えるお金」の予算を設定する
- 費目ごとの予算を細かく分けすぎると管理が大変になるので、「毎月使えるお金」の予算はざっくりでOK
無駄のない家計の基本は、先取り貯蓄にあります。
【毎月の収入-先取り貯蓄=毎月使えるお金】
とし、「毎月使えるお金」の中で何にいくら使うのか、費目ごとにざっくりとした予算を決めましょう。
筆者がオススメする費目の分け方は、以下のとおりです。
<「毎月使えるお金」の費目の分け方例>
| 固定費(毎月固定で発生する費用) | 住居費、生命保険料、保育園や幼稚園の保育利用料、水道光熱費や通信費の基本料金部分など |
|---|---|
| 変動費(毎月変動する費用) | 食費、日用品費、交際費、水道光熱費の変動費部分など |
| 特別費(1年のうち数回発生する大きな支出) | 冠婚葬祭費、旅行代、家具家電の買い替え費など |
上記の表を目安に支出を分類し、「固定費」や「変動費」の予算を決めてください。
費目ごとにざっくりとした予算を立ててお金の使い方を意識することで、家計の無駄を防ぎやすくなるでしょう。
とはいえ、「そもそも、予算をどう設定したらいいかわからない」という人もいると思います。
予算の設定方法に不安がある、どの費目が無駄遣いなのかわからないという人は、家計管理のプロであるファイナンシャル・プランナーに相談するのも一つの方法です。
家計簿をファイナンシャル・プランナーに見せ、
- 支出の中で改善できるポイントはあるのか
- 収入から見た適正な支出額はいくらか
- 無駄遣いになっている費用はどれか
第三者へ相談すると、自分では気づかなかった思わぬ無駄を発見しやすくなります。
また費目ごとに適切な予算を設定できれば、貯蓄額を増やすことにもつながるでしょう。
家計を改善するためにも、専門家であるファイナンシャル・プランナーへの相談をうまく活用してみてください。
■家計簿は無理に続けなくてもいい

家計簿は「続けなければならないもの」と思っていませんか?
しかし筆者は、家計簿を無理に続ける必要はないと考えています。
なぜなら家計簿は、無駄遣いを把握して家計を改善するためのツールにしかすぎないからです。
ツールがなければ、無駄遣いを直せない。
そんな家計は、逆に危険ではないでしょうか。
家計簿を付ける最終目的は、「家計を見直してしっかり貯蓄すること」のはずです。
ただのツール・手段を目的にしてしまうのは、本末転倒と言えます。
家計の無駄に気付いたら、無駄をなくしてそのぶん貯蓄を増やすだけで良いのです。
「最近、無駄遣いが増えたかも?」と気になったときだけ、集中的に家計簿をつける。
その都度、家計を改善していく。
これを繰り返し、家計簿がなくても問題のない状態にしていくのが理想の家計と言えるでしょう。
■まとめ

家計の状態を見える化して無駄遣いをなくし、そのぶん貯蓄する。
そのために使うのが家計簿です。
つまり家計簿は目的ではなく、ただの手段です。
クレジットカード払いを家計簿に付けるときは、ざっくりでかまいません。
家計簿の付け方よりも、支出を把握して無駄をなくすことにこだわりましょう。
支出を把握できたら、あとは無駄なポイントを見直すだけです。
もし「家計の無駄・改善ポイントがわからない」場合は、ファイナンシャル・プランナーなどの専門家に相談するのも一つの方法です。
第三者に見てもらえば、思わぬ改善点に気付けるかもしれません。
ぜひFPナビで、無料相談をお試し下さい。
ときには専門家に頼りつつ、家計簿の付け方を見直してみてください。
※この記事は2020年12月時点の法律・情報に基づき作成しているため、将来、法律・情報・税制等が変更される可能性があります。
執筆者
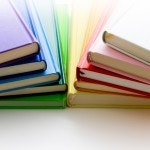
服部 椿
プロフィール:FP分野専門のフリーランスライター。
子育て中のママFPとして、子育て世帯に役立つ家計や投資、お金に関する情報を発信中。
保有資格:2級FP技能士