教育・子育て
エアコンを節約しすぎてない?子供を守る熱中症対策はこれ!

天気がいいと、気分があがってお出かけしたくなりますよね。
でも油断は禁物。涼しい日でも熱中症のリスクはあるんです。
そこで今回は、身近な危険である熱中症について情報をまとめました。
- 熱中症になりやすいリスク要因
- 熱中症の予防方法
- 熱中症対策と節約の両立
にわけて解説していきます。
家族の健康と家計を守りたい方は、ぜひご覧ください。
熱中症になりやすいリスク要因は3つ
環境省によると、熱中症を引き起こす条件には「環境」「からだ」「行動」があるそうです。
【環境】
- 気温が高い
- 日差しが強い
- 急に暑くなった
- 湿度が高い
- 締め切った屋内
- 熱波の襲来
- 風が弱い
- エアコンの無い部屋
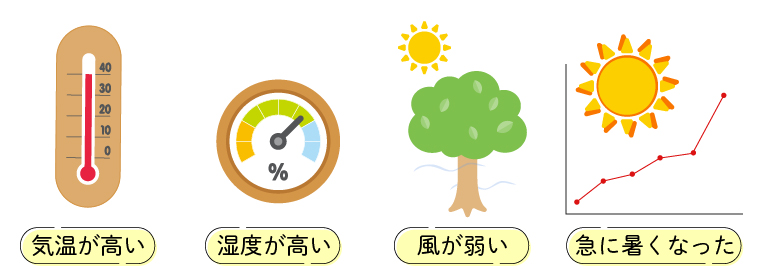
【からだ】
- 高齢者や乳幼児、肥満の方
- 下痢やインフルエンザでの脱水状態
- 糖尿病や精神疾患といった持病
- 二日酔いや寝不足といった体調不良
- 低栄養状態

【行動】
- 激しい筋肉運動や、慣れない運動
- 長時間の屋外作業
- 水分補給できない状況

「炎天下の中、水分補給をせずに部活動をすれば熱中症になりそう」というイメージはありますが、実はそれだけがリスクではないんですね。
乳幼児というだけでも大人よりリスクがあがりますし、気温だけでなく「風や湿度」も関係があるのです。
これらの要因をただしく知ることが、熱中症予防の第一歩だと言えます。
熱中症の予防方法
熱中症予防には正しい知識と同じように、対策が必要になります。
今日からでもできる熱中症予防を、リスクの要因ごとにご紹介します。
環境要因への対策:屋外の場合

気温だけで「そんな暑くないから大丈夫」と判断せず、必ず屋外では帽子をかぶりましょう。
定期的な水分・塩分補給も必須です。
最近では水分だけでなく、糖分・塩分もバランスよく摂ることが普及してきました。
万能なのはスポーツドリンクですが、子供に飲ませるときには注意が必要です。
子供の年齢によっては濃すぎるため、水で薄めて飲ませましょう。もしくは水と一緒に塩分入りのタブレットやビスケットなどを食べるのもオススメ。
運動前・運動中・運動後に意識して摂取しましょう!
遊ぶ場所は、川沿いや緑の多い公園などを選ぶのがポイントです。
公園内に微細ミストや遮熱性の日除けがあるところも増えてきました。
熱中症対策のグッズを取り入れてみるのもオススメです。
たとえばベビーカーやチャイルドシート、抱っこ紐などに入れられる冷却グッズがあります。
自分で歩ける年齢の子供や親には、首に巻くタイプも。
子供と外で遊ぶときは、このように万全な持ち物と場所選びが重要になりますね。
環境要因への対策:室内の場合
室内でも、熱中症になるリスクはあります。
定期的な水分補給に加え、「室温を下げる」「除湿する」「換気する」の3点が重要です。
〇室温を下げる
エアコンの利用だけでなく、直射日光を遮る工夫もしましょう。グリーンカーテンやサンシェード、遮熱カーテンなどが効果的です。電気ポッドやPCなど、使っていない家電のコンセントを抜くだけでも、室温の上昇を抑えられます。
〇除湿する
除湿機やエアコン、除湿剤などを活用しましょう。部屋干しをしている方は、換気を徹底するかサーキュレーターを併用すると湿度を抑えられます。
〇換気する
対角上の窓を開けるなど、定期的な換気が必要です。最近の家には24時間換気システムがついていますが、フィルターの詰まりなどでうまく機能していないことも。意識的に換気しましょう。
子供が別室で遊んでいるときは、水分補給だけでなく室温や湿度も気にかけてあげる必要がありますね。
からだ要因への対策
からだの要因とは、熱中症になりやすい人のことでした。
高齢者、子供、障害のある人、体調の悪い人などがあたります。
たとえば小さな子供は体温調節機能が発達していないので、熱中症のリスクが高いのです。体が小さい分、アスファルトからの照り返しを受けやすいのも要因ですね。
できる対策としては、
- 体調がすぐれないときや、病み上がりのときは外出を控える(もちろん大人も)
- 子供と外出するときは大人の体感で判断しない
があります。
子供と大人では体感温度が違う上、子供も自分では正確な暑さを感じられません。体温調節機能が整っていないからです。
どちらも「この暑さなら大丈夫」と軽く判断しないようにしましょう。
ここでは環境省と気象庁が発表する、「熱中症警戒アラート」が参考になります。
都道府県ごとにとくに暑くなると予測された当日や前日に、注意を呼びかける情報です。
メールやLINE通知などもあるので、登録しておくと安心ですね。
行動要因への対策
最後に行動要因です。熱中症の行動要因には、激しい運動などがあります。
公園遊びなどは夢中になりがちですが、きちんと時間を区切って水分・塩分補給をしましょう。
スマホでタイマー設定するのがオススメです。
また遊ぶ時間も大事。
陽が高い時間はできるだけ避け、短時間で帰るように心がけましょう。
屋内施設が近くにあるのなら、室内での休憩もうまく取り入れるといいですよ。
熱中症対策と節約の両立
熱中症のリスク要因と予防法をお伝えしました。その中の「室内での熱中症対策」は、電気代が気になるところではないでしょうか。
エアコンや除湿機をフル稼働してしまう夏は、どうしても電気代がかかります。節約をしたい家庭にとっては、悩ましいところですよね。
そこでここからは、熱中症対策をしながらでも電気代を抑える方法と、もう一歩踏み込んだ「節約の本質」について考えていきたいと思います。
熱中症対策をしながらでも電気代を抑える方法

エアコンはつけっぱなしの方がいいとよく言われます。
こまめにON/OFFしない分、節約にはエアコンの設定気温を上げる工夫が必要です。
冷房時の温度設定を1℃高くすると、約13%(約70W)の消費電力削減になるのだとか。
そのためには、
- フィルターの掃除はこまめにする
- 室外機の周りに物を置かない
- 扇風機やサーキュレーターを併用して風向きを上手に調整する
などが有効です。
(参考)環境省のCOOL CHOICE:家庭でできる節電アクション
とくにサーキュレーターは近年注目のアイテムでオススメです。消費電力が小さいものの、製品によっては360度の首振り機能がついており、効率的に空気を循環します。部屋干しでの湿度が気になる場合、サーキュレーターの併用で乾きが早くなる効果も。
つまり熱中症リスクの「室温」「湿度」にも有効なのです。
先にご紹介した「グリーンカーテンやサンシェード、遮熱カーテン」なども、エアコンの設定温度を上げる効果がありますね。
これらのアイテムを効率よく取り入れて、エアコンの電気代を抑える工夫をしましょう。
節約の本質、忘れていませんか?
熱中症対策と節約の両立についてお話しましたが、劇的な節約!!…とは正直言えません。グッズを取り入れるなら、その購入費用もかかりますよね。
エアコンの電気代上昇を少し抑え、一方ではグッズを購入する。もしかするとトントンになる家庭があるかもしれません。
しかし、そもそも節約で大事なことはなんでしょうか。我慢をすればするほど節約している気持ちにはなりますが、必ずしも努力と節約が比例するわけではありません。食費や光熱費の節約に必死になりすぎて、他に削れるところを見逃している家庭は意外に多いのです。
熱中症は、重症の場合入院のリスクもある怖い病気です。でも家庭の中で対策できる病気でもあります。電気代を心配して節約しすぎてしまい、もし入院になるほどの熱中症になってしまえば…。
少しの節約で家族の健康が損なわれてしまえば、本末転倒ですよね。食費だって同じです。削り過ぎれば将来の医療リスクが高まるかもしれません。
家族の健康を考えれば、無理な節約は避けましょう(もちろん無駄遣いはしないよう、適正ラインの見極めは必要になります)。
家計の出費を抑えたいなら、まずは他の項目の見直しをオススメします。たとえば家賃やスマホ利用料、保険料などのいわゆる固定費です。
食費や光熱費節約のように日々我慢するのではなく、1度見直すだけ。しかも家庭によっては、食費などより節約額が大きいこともあります。「がんばった感」がないかもしれませんが、がんばりすぎると反動がくるリスクだってあります。
家計を見直したいなら、まずは固定費から!これが家計見直しの王道なのです。
まとめ

熱中症になりやすいリスク要因とその予防対策、そして節約についてお話しました。
かんたんにまとめてみます。
- 熱中症を引き起こす条件には「環境」「からだ」「行動」があり、それぞれ予防対策が必要
- 「乳幼児ならでは」のリスクもあるため、大人が水分補給や室温設定など気にかけてあげる必要がある
- 室内での熱中症対策にはエアコンが必須。電気代を抑えるために、設定気温をあげる工夫を
- 電気代だけが家計の節約ではない。効率よく見直すなら固定費から
大事な家族の健康はもちろん、できれば家計も守りたいですよね。
「自分の家族構成で、今の食費や光熱費は適正なのか?」
「他にどんな支出項目を減らせるの?」
そんな家計の診断は、お金の専門家であるFP(ファイナンシャル・プランナー)に相談できます。
熱中症対策を万全にしつつ、家計の見直しもぜひすすめてみてくださいね。
※この記事は2021年6月時点の法律・情報に基づき作成しているため、将来、法律・情報・税制等が変更される可能性があります。
出典
「熱中症予防情報サイト【熱中症の予防方法と対処方法】」(環境省)
https://www.wbgt.env.go.jp/doc_prevention.php
「熱中症警戒アラート」(環境省)
https://www.wbgt.env.go.jp/alert.php
「COOL CHOICE【家庭でできる節電アクション】」(環境省)
https://ondankataisaku.env.go.jp/coolchoice/setsuden/home/saving03.html
執筆者
ニッセンライフ編集部
ニッセンライフの編集部に所属する、働く双子ママ。
「遊びたい盛り、食べたい盛り、論破したい盛り」の双子を育てながら、
子育て世代の心が軽くなるような情報を発信しています。





