仕事
フリーランスの労災対象者が拡大。それでも薄い社会保障を手厚くする方法

「フリーランスでも労災保険に入れるって本当?」
実はフリーランスでも、特別加入制度を使えば労災保険に入ることは可能です。
2021年4月1日と9月1日に制度対象者の範囲が広がり、自転車を使用して貨物運送事業を行う者や俳優・声優など、新たに労災保険に入れる方が増えました。
とはいえ、すべてのフリーランスが労災保険に加入できるわけではありません。
筆者もフリーランスの端くれですが、ライターは特別加入制度の対象外です。労災補償を含め、保険や年金などの社会保障は、まだまだ会社員に及ばないと痛感しています。
今回は、フリーランスでも入れる労災保険の特別加入制度について解説しながら、個人で社会保障を手厚くする方法も案内します。
※フリーランスという言葉に公的な定義はありません。ここでは「個人事業主として、雇用されずに1人で働く人」をフリーランスとしてご案内しています。
フリーランスでも入れる労災保険の特別加入制度とは
労災保険とは、労働者として事業主に雇用され、賃金を受ける人が対象です。
そのため自営業や個人事業主など、フリーランスとして雇用されずに働いている人は、労災保険の対象外です。
しかし一部の業務に従事している場合は、たとえフリーランスでも任意で労災保険に加入できます。
これが「労災保険の特別加入制度」です。
2021年4月1日と9月1日に特別加入制度の対象範囲が広がり、新たに労災保険に加入できるフリーランスが増えました。
対象者について、詳しく解説していきましょう。
2021年4月から広がった特別加入制度の対象範囲
2021年4月1日から、労災保険に加入できるフリーランスの対象範囲が広がりました。
従来の対象者と、4月から追加になった対象者は以下のとおりです。
<2021年4月1日以前の特別加入者の範囲>
(以下引用)
①自動車を使用して行う旅客または貨物の運送の事業
(個人タクシー業者や個人貨物運送業者など)
② 土木、建築その他の工作物の建設、改造、保存、原状回復(注)、修理、変更、破壊もしくは、解体またはその準備の事業
(大工、左官、とび職人など)
③漁船による水産動植物の採捕の事業(⑦に該当する事業を除きます)
④林業の事業
⑤医薬品の配置販売(医薬品医療機器等法第30条の許可を受けて行う医薬品の配
置販売業)の事業
⑥再生利用の目的となる廃棄物などの収集、運搬、選別、解体などの事業
⑦船員法第1条に規定する船員が行う事業
(引用ここまで)
引用元:「特別加入制度のしおり」より「1.特別加入者の範囲」(厚生労働省)
<2021年4月1日に追加された特別加入者の範囲>
| 芸能関係作業従事者 | 俳優、声優、舞踊家、歌手や作詞・作曲家などの音楽家、照明や大道具・衣装製作といった各種芸能制作に関わる方 |
|---|---|
| アニメーション制作作業従事者 | キャラクターデザインや脚本など、アニメーション制作関係の作業をする方 |
| 柔道整復師 | 「柔道整復師法第2条に規定する柔道整復師が行う事業」を、労働者を使用せずに行う一人親方や、一人親方が行う事業に従事される方 |
| 創業支援等措置に基づき事業を行う方 | 高年齢者雇用安定法で規定する創業支援等措置に基づき事業を行う方 |
2021年9月から広がった特別加入制度の対象範囲
| 自転車を使用して貨物運送事業を行う者 | 飲食物等のデリバリーサービスなど |
|---|---|
| ITフリーランス | ITコンサルタントやシステムエンジニアなど労働者以外の方であって、「情報処理に係る作業」を行う者 |
いずれの場合も、一人親方のフリーランスが労災保険へ加入するためには、窓口となる「特別加入団体」で申し込み手続きを行う必要があります。
特別加入団体については、お住まいの労働基準監督署または労働局にてご確認ください。
加入範囲は広がっても、フリーランスの社会保障は手薄い
今回の労災保険対象範囲拡充は、フリーランスの環境整備に取り組む国の政策の1つです。
内閣官房調査によると、フリーランス人口はおよそ462万人。
コロナ禍で多様な働き方が求められる中で、今後もフリーランス人口は増えるでしょう。
同時に、フリーランスの環境整備への期待も高まります。
とはいえ2021年時点では、まだまだフリーランスの社会保障は薄い状況です。
<会社員とフリーランスの社会保障の違い>
| フリーランス | 会社員 | |
|---|---|---|
| 公的健康保険 (病気やケガなどの保障) | 国民健康保険 | 健康保険 |
| 公的年金 (老後・障害・遺族保障) | 国民年金 | 厚生年金 |
| 雇用保険 (失業・妊娠・出産時などの保障) | 原則、加入できない | あり |
| 労災保険 (仕事中や通勤時の病気・ケガ・死亡時などの保障) | 特別加入制度であれば一部のフリーランスのみ加入できる | あり |
たとえば国民健康保険には、会社員のような「傷病手当金」はありません。
病気やケガで仕事を休んでも、国民健康保険から何か支給されるわけではないのです。
公的年金も、会社員であれば国民年金の基礎部分に、会社が上乗せする厚生年金部分が上乗せされます。しかしフリーランスにはそういった上乗せ部分がないため、もらえる年金額は会社員より少ないのが一般的です。
また妊娠・出産・失業給付のある雇用保険も、フリーランスは原則加入できません。
妊娠・出産で仕事を休めば、休んだぶんだけ収入がなくなるのがフリーランスです。
たとえ仕事がなくなって失業状態になっても、雇用保険の失業給付のような補償はありません。
このように、まだまだフリーランスの社会保障は充実しているとは言えません。
フリーランスとして生きていくためには、個人であらゆる保障に備えておくことが大切です。
【現役フリーランスが解説】老後・病気・ケガなどに個人で備える方法

ここでは現役フリーランスとして生活する筆者の経験もふまえ、足りない社会保障を個人で備える・手厚くする方法を紹介します。
フリーランスが気になる保障別に、個人で加入できる制度や保険をまとめました。
| 制度・保険など | 備えられる保障やメリット | 概要 |
|---|---|---|
| 国民年金基金 | ・老後の保障 ・税制上の優遇措置による節税効果あり | フリーランス(国民年金第一号被保険者)が入れる公的年金の上乗せ制度。 終身年金で、年金額があらかじめ確定しているため確実に老後資金を用意したい人向け。手数料不要 |
| 個人型確定拠出年金(iDeCo) | ・老後の保障 ※運用次第では元本割れの可能性もある ・税制上の優遇措置による節税効果あり | フリーランス(国民年金第一号被保険者)も会社員も入れる私的年金制度。 自身で掛金を運用して増やす制度のため、運用方法によっては元本割れするが、元本以上の年金を用意できる可能性もある。 リスクを取って年金額を増やしたい人向け。運用・管理手数料が必要 |
| 小規模企業共済 | ・老後の保障 ・事業廃業・緊急時の保障 ・税制上の優遇措置による節税効果あり | 一定の要件を満たすフリーランス・事業者が入れる退職金制度。老後だけではなく、事業を廃業する際も共済金を受け取れ、事業経営が困難な際は低金利の貸付制度を利用できる。ローリスクで確実に老後や廃業時の資金を用意したい人向け |
| 民間の医療保険 | ・病気やケガの保障 ・保険料控除による節税効果あり | 民間の保険会社が販売する病気やケガの民間保険。病気やケガで通院・入院・手術した際などに一定の保障を受けられる |
| 民間の就業不能保険 | ・病気やケガで働けないときの補償(保障) ・保険料控除による節税効果あり | 民間の保険会社が販売する、病気やケガで働けないときの民間保険。一定の就業不能状態になったときに一定の保障を受けられる |
| 国民健康保険組合 (国保組合) | ・病気やケガの保障 ・保険料の節約効果がある場合もある ※加入する組合により異なる | 同種同業者のための保険組合。 組合によって独自の付加給付(医療保障)を用意していたり、固定保険料制を採用していたりする。そのため国民健康保険にはない独自の医療保障を得たり、保険料を抑えたりできる可能性がある |
筆者がフリーランスになって一番気になったのが、老後や働けないときの保障でした。
そのため「自分年金」と称してiDeCoを、さらに「自分保険」と称して民間の保険に加入しています。
また毎月の国民健康保険料も、フリーランス家計の負担になりやすいポイントです。
筆者自身、住んでいる自治体の国民健康保険料が高いと感じていたため、自身の業種で入れる国民健康保険組合を探して切り替えをしました。
その結果保険料を節約でき、組合独自の付加給付も得られて非常に満足しています。
こうした各種保障・制度はすべて「任意加入」です。
つまりフリーランスは自発的に動かなければ、自分の環境を改善することはできません。
働く環境を整え、足りない社会保障を充実させるのは自分次第です。
上記で紹介した制度や保険を元に、自身の環境を見直してみてくださいね。
まとめ
フリーランスでも、特別加入制度を使えば任意で労災保険に加入できます。
2021年4月と9月から対象者が広がり、システムエンジニアやITコンサルタント、アニメーション制作関係者の方も加入できるようになりました。
このように、フリーランスの環境を整備する流れになってきてはいるものの、現状ではまだまだ社会保障が手薄い状況です。
フリーランスの老後や病気・ケガの保障を手厚くできる制度・保険は、すべて任意加入。つまり自分自身で動かなければ、状況は何も変わりません。
ご紹介したiDeCoや小規模企業共済、民間の保険などをうまく活用し、自らフリーランス環境を整えていきましょう。
※この記事は2021年9月時点の法律・情報に基づき作成しているため、将来、法律・情報・税制等が変更される可能性があります。
出典
「令和3年4月1日から労災保険の「特別加入」の対象が広がります」(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyouroudou/roudoukijun/rousai/kanyur3.4.1.html
「令和3年9月1日から労災保険の「特別加入」の対象が広がります」(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/rousai/kanyu_r3.4.1_00001.html
「フリーランス実態調査結果」(首相官邸)
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/zensedaigata_shakaihoshou/dai7/siryou1.pdf
執筆者
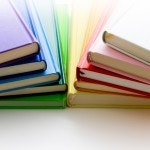
服部 椿
プロフィール:FP分野専門のフリーランスライター。
子育て中のママFPとして、子育て世帯に役立つ家計や投資、お金に関する情報を発信中。
保有資格:2級FP技能士





