住まい
住宅ローンの借入可能額の計算方法とは?

「いくらの住宅ローンが組めるのだろう」と気になる方は少なくありません。
住宅ローンの借入可能額によって、住宅の購入予算が変わってくるためです。
金融機関は、借り入れる人の年収だけで住宅ローンの審査をしているのではありません。
また審査の基準や借入可能額の計算で用いられる数値は、金融機関によって異なります。
本記事では、金融機関が住宅ローンの融資審査で確認しているポイントや、借入可能額の計算方法、借り入れるときの注意点などを解説します。
住宅ローンの借入可能額の計算に影響がある要素
金融機関は、住宅ローンの審査で「年収」や「他の借入額」などを確認し「返済比率」や「審査金利」を用いて借入可能額を計算します。
ここでは住宅ローンの審査で用いられる「返済金利」や「審査金利」について解説します。
返済比率
住宅ローンの審査では、年収のうちローンの返済に充てても良いとされる割合「返済比率」が、基準の範囲内であるか確認されます。
たとえば、全期間固定金利型住宅ローンである「フラット35」の返済比率の基準は、以下のとおりです。
- 年収400万円未満:30%以下
- 年収400万円以上:35%以下
仮に年収が350万円であった場合、年間で350万円×30%=105万円までをローンの返済にあてられるとして、フラット35の借入可能額が計算されます。
返済比率の計算では、借り入れ予定の住宅ローンだけでなく、すでに借り入れている「自動車ローン」や「教育ローン」なども含まれます。他の借り入れが多いほど、住宅ローンの借入可能額は少なくなるのです。
返済比率の設定は、金融機関によって異なります。中には年収が700万円や800万円など高額である場合に、返済比率を40%にして審査をする金融機関もあります。
審査金利
審査金利とは、住宅ローンの審査で用いられる金利です。
借り入れ時に毎月の返済額や利息額を計算する際に用いられる「適用金利」とは値が異なるだけでなく、一般には公開されてもいません。
変動金利の場合、審査金利は3.5〜4.0%です。2021年12月現在、変動金利がおおむね0.4%台であることを考えると、相場よりも高い値といえます。これは、金利が上昇しても返済できるかを審査するためです。
一方、全期間固定金利は、返済期間中に金利や返済負担が上昇しません。そのため全期間固定金利型住宅ローンの審査金利は、適用金利と同じ値となります。
住宅ローンの借入額をシミュレーション
住宅ローンの借入可能額を、年収や返済期間、金利別にシミュレーションします。
借入可能額の計算方法は、以下のとおりです。
- 借入可能額=(年収×返済比率÷12−他の借入の返済額)÷「100万円を審査金利で借りた場合の毎月の返済額」×100万円
なお住宅ローンは、1万円単位での借り入れができないため、計算結果から1の位の数字を切り捨てて借入可能額を算出しています。
年収別の借入可能額
年収ごとに借入可能額がどのように異なるのか、シミュレーションで確認してみましょう。
年収以外の条件は、以下のとおりです。
- 返済期間:35年
- 審査金利:3.5%
- 審査金利3.5%で100万円を35年借りた場合の返済額:4,133円
- 他の借り入れ:なし
返済比率は、以下のとおりとします。
- 年収400万円未満:30%
- 年収400万円以上600万円未満:35%
- 年収600万円超:40%
以上の条件における借入可能額は、以下のとおりとなりました。
| 年収 | 借入可能額 |
|---|---|
| 年収300万円 | (300万円×30%÷12)÷4,133円×100万円≒1,810万円 |
| 年収400万円 | (400万円×35%÷12)÷4,133円×100万円≒2,820万円 |
| 年収500万円 | (500万円×35%÷12)÷4,133円×100万円≒3,520万円 |
| 年収600万円 | (600万円×40%÷12)÷4,133円×100万円≒4,830万円 |
| 年収700万円 | (700万円×40%÷12)÷4,133円×100万円≒5,640万円 |
年収が上がると、借入可能額は増えます。
年収300万円から年収600万円へ2倍に増えると、借入可能額は1,810万円から4,830万円へ約2.67倍も増えています。
これは、年収300万円の返済比率が30%であるのに対し、年収600万円は40%であるためです。
なお職業によって、住宅ローン審査での年収の判定方法が異なります。
会社員や公務員などの給与所得者は、源泉徴収票に記載されている「税込年収」で審査されるのに対し、自営業やフリーランスは収入から必要経費を引いた「所得」で審査されます。
返済期間別の借入可能額
次に返済期間が変わると、借入可能額がどのように変化するのかシミュレーションで確認してみましょう。
返済期間以外の条件と試算結果は、以下のとおりです。
- 年収:400万円
- 返済比率:35%
- 審査金利:3.5%
- 他の借り入れ:なし
| 返済期間 | 審査金利3.5%で 100万円を借りた場合の返済額 | 借入可能額 |
|---|---|---|
| 15年 | 7,149円 | (400万円×35%÷12)÷7,149円×100万円≒1,630万円 |
| 20年 | 5,800円 | (400万円×35%÷12)÷5,800円×100万円≒2,010万円 |
| 25年 | 5,006円 | (400万円×35%÷12)÷5,006円×100万円≒2,330万円 |
| 30年 | 4,490円 | (400万円×35%÷12)÷4,490円×100万円≒2,590万円 |
| 35年 | 4,133円 | (400万円×35%÷12)÷4,133円×100万円≒2,820万円 |
返済期間が長いほど、借入可能額は増えています。借入額を増やしたい場合は、返済期間をできる限り長くするのも方法の1つです。
返済期間の上限は、多くの金融期間が35年としています。ただし、ほとんどの金融機関が完済時の年齢を80歳未満としているため、年齢によっては35年の住宅ローンを組めない場合があります。
審査金利が異なる場合の借入可能額
審査金利が異なると、借入可能額に変わるのでしょうか?
審査金利が3.5%の金融機関と4.0%の金融機関で借入可能額を比較してみましょう。
審査金利以外の条件は、以下のとおりとします。
- 年収:400万円
- 返済比率:35%
- 返済期間:35年
- 他の借り入れ:なし
審査金利が3.5%で100万円を35年借りた場合の返済額は、4,133円です。
よって借入可能額は(400万円×35%÷12)÷4,133円×100万円≒2,820万円となります。
審査金利が4.0%になった場合、100万円を35年借りた場合の返済額は4,428円です。
借入可能額を計算すると(400万円×35%÷12)÷4,428円×100万円≒2,630万円となりました。
シミュレーションの条件において、審査金利が3.5%から4.0%へ上がると、借入可能額は190万円減少する結果となりました。
他のローンがある場合の借入可能額
他の借り入れがある場合の借入可能額をシミュレーションします。
条件は、以下のとおりです。
- 年収:400万円
- 返済比率:35%
- 審査金利:3.5%
- 審査金利3.5%で100万円を35年借りた場合の返済額:4,133円
他の借り入れがない場合、借入可能額は(400万円×35%÷12)÷4,133円×100万円≒2,820万円です。すでに自動車ローンを借り入れており、毎月30,000円を返済に充てていた場合、借入可能額は以下に変化します。
- 借入可能額(400万円×35%÷12-30,000円)÷4,133円×100万円≒2,090万円
毎月30,000円の返済があると、住宅ローンの借入可能額が730万円も減る結果となりました。
住宅を購入するときは今後のライフプランを踏まえて資金計画を立てる
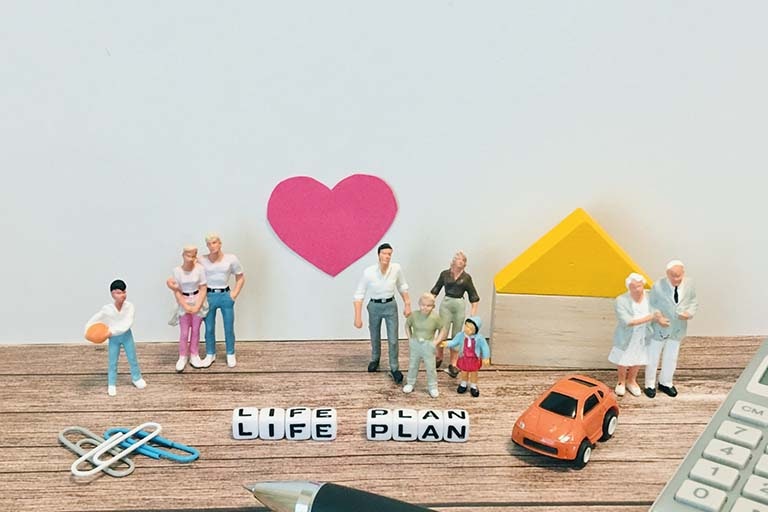
住宅購入の資金計画を立てるとき「3,500万円程度まで借りられそうだから、貯金の300万円と合わせて3,800万円までの物件が買える」と考えると、失敗する恐れがあります。
住宅を購入するときは、今後のライフプランを踏まえて予算を設定する必要があるためです。
住宅購入時に考慮すると良いライフプランの例は、以下のとおりです。
- 自動車の購入・買い替え
- 子どもの進学
- 転職・独立
- 老後生活
子どもの進学と住宅ローンの返済が重なると、金利の高い教育ローンの借り入れが必要となり、返済負担が家計を圧迫する恐れがあります。奨学金を借り入れるのも方法の1つですが、返済するのは子どもであるため慎重に利用を検討する必要があります。
また老後生活を考えずに、返済期間を長くして住宅ローンを借り入れてしまうと、返済負担が老後の家計を圧迫し、生活が苦しくなるかもしれません。
将来のことは、誰にも分かりません。
かといって無計画に住宅を購入すると、金銭的なリスクが発生しやすくなります。
住宅を購入するときは、今後のライフプランを考えて、返済計画を立てることが大切です。
とはいえ、ライフプランの作成は専門的な知識がなければ困難でしょう。
そこで住宅を購入するときは、信頼できるファイナンシャル・プランナーに相談するのがおすすめです。
- お客さまのご要望や相談内容に合わせて、FPを選んで相談ができる
- 平日・土日祝問わず、10時から19時であれば、希望の日時が選べる
- ご自宅へ訪問はもちろん、FP事務所や最寄りのカフェ・レストランで相談できる
FPナビに登録しているFPは専門資格保持だけではなく、ニッセンライフ独自の認定制度を設けることで、専門性の高さとお客さまの満足度の向上に努めています。
<FPナビが選ばれる理由とは>
サービスに関するお問合せなどありましたら、お気軽にお電話・ご連絡ください。
<WEBフォームから問い合わせる>
<電話で問い合わせる>
0120-880-081
月曜~金曜 9:00~19:00
土曜・祝日 9:00~18:00
※この記事は2021年12月時点の法律・情報に基づき作成しているため、将来、法律・情報・税制等が変更される可能性があります。
出典
「【フラット35】ご利用条件」(住宅金融支援機構)
https://www.flat35.com/loan/flat35/conditions.html
執筆者

品木彰
保険、不動産、住宅ローンなどの記事を執筆するフリーランスライター
大手生命保険会社、人材会社の勤務を経て2019年1月にして独立。記名記事多数。
保有資格:2級FP技能士





