教育・子育て
子供の教育費に必要な額はいくら?教育費の平均や目安はどれくらい?
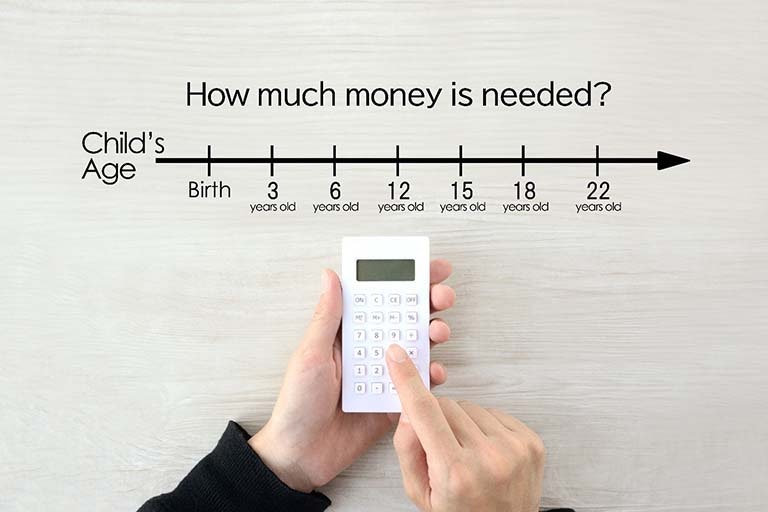
子育て世代にとって「教育費」は大きな出費です。
授業料や学習費としてまとまった額を一気に支払うことも多いため、いざというときに慌てないよう計画的に貯めておく必要があります。
今回は、子供の幼稚園から大学までにかかる教育費の目安や、教育費を貯めるうえで気をつけたいポイントについても解説します。
教育費に漠然とした不安を抱えている方は、ぜひ参考にしてください。
教育費に必要な金額
下記は、子供を幼稚園から大学まで通わせたときの「教育費」の目安です。
ここでいう教育費とは、学校教育だけではなく学校外活動の費用も合わせた金額を指します。
子供の教育費として平均約1,000万円~約2,500万円が必要になるといわれており、一気に必要になるものではありません。
そこで、この章では進学タイミングで必要になるお金をまとめました。
幼稚園児の教育費
教育費は公立に通うか私立に通うかで変わりますが、その差は幼稚園の時点で生まれます。
文部科学省の平成30年度子供の学習費調査によると、公立幼稚園では1年間に22万3,647円、私立幼稚園では1年間に52万7,916円と、公立と私立では、約2.4倍もの差があるのです。
子供がまだ小さいこの時期は、習い事・部活動・塾といった課外活動の費用はさほど負担になりません。
また、2019年に幼児教育無償化が始まったことで、条件に該当すれば公立・私立ともに幼稚園が無償化され、幼稚園の預かり保育も月額1.13万円まで無償となりました。
そのため、公立・私立を問わず教育費の負担が減っているのは家計に嬉しいところです。
ただし、最も教育費が低く抑えられるのは幼稚園の時期です。制度をうまく活用しながら、浮いたお金はコツコツ蓄えておきましょう。
小学生の教育費
小学校6年間でかかる教育費の平均額は、公立小学校で年間32万1,281円、私立小学校の場合、年間159万8,691円となっています。そのため、小学校だけで教育費の差は約5倍と大幅に変わります。
公立では授業料がない代わりに「図書・学用品・実習材料費等」などの支出が多く、一方で、私立では「授業料」の支出が53.7%と教育費の半分以上を占めています。
私立小学校の学習費は、私立幼稚園・私立中学・私立高校と比較しても最も高額です。
もしも子供を私立の小学校に通わせる場合は、子供が生まれてからすぐにでも資金を積み立てておき、授業料の納付に備える必要があります。
中学生の教育費
中学でかかる教育費は、公立中学校で1年あたり48万8,397円、私立中学校の場合は140万6,433円となっており、公立と私立では3倍ほどの違いがあります。
義務教育なので公立の授業料は無償ですが、私立では授業料が発生するという点で金額に差があります。
なお、公立では予習・復習・補習などの支出が私立よりも高くなる傾向があり、公立の幼稚園・小学校・高校と比較しても最も高い補助学習費が必要になっています。
私立中学の受験を希望する場合は、受験のための対策費用を考慮しなければなりません。
また、公立を想定している場合でも油断せず、子供が幼稚園・小学校に通っている間に中学校から大学進学までの費用をコツコツ貯めておくことで、余裕を持って我が子の学びをサポートできるでしょう。
高校生の教育費
高校生の教育費は、1年間で公立高校は45万7,380円、私立高校では年間平均が96万9,911円となっており、公立と私立で2倍の差がありますが、小学校や中学校と比べて、教育費の差は小さくなっています。
学校教育費のうち「授業料」及び「学校納付金等」の割合は、公立高校では約30%であるのに対して、私立高校では約62%を占めています。
学校外活動費については公立・私立ともに自宅学習・学習塾・家庭教師に使う支出の割合が最も高くなっています。
なお、高校では公立・私立を問わず学費を援助する公的な制度「高等学校等就学支援金制度」があるため、年収が約910万円未満世帯であれば、負担を軽減できる可能性があります。
大学生の教育費
大学卒業までにかかる費用の平均金額は約680.7万円です。大学においても国公立と私立では支出に差があり、国公立大学では約481.2万円に対し、私立大学に入学した場合は文系で約689.8万円、理系で約821.6万円となっています。
国公立と私立の間では少なくとも約208.6万円の差があり、私立大学については文系・理系どちらを選ぶのかによっても費用が異なることがわかります。
なお、子供1人当たりの入学費用は、高専・専修・各種学校が約50.2万円、短大が約76.5万円、大学が約79.2万円となり、入学前に納付しなくてはなりません。
奨学金が振り込まれるのは入学後ですから、奨学金を利用する場合でも入学金を一括で払えるくらいの貯蓄は必須です。
また、大学進学と同時に一人暮らしをする子供に仕送りをする場合、年間約95.8万円が必要になるでしょう。
月額約79,800円と重たい出費となりますので、教育費以外の出費が大きくなることも想定しておく必要があるでしょう。
教育費はいつから貯めるべき?
高校までの教育費については、月々の給料からあらかじめ引いておいたり、ボーナスを丸ごと貯めたりすることが理想的です。
高校入学から大学卒業までの7年間でかかる金額は、平均で942.5万円。
一人暮らしの引越し代や仕送りにかかる金額、大学の入学費用や授業料は一括で支払うため、あらかじめ300~500万円程度のまとまった金額を用意しておくと安心です。
進路によって大きく金額が変わり、また子育てにかかるのは教育費だけではないので、教育費は子供が生まれた直後から少しずつ貯めていきましょう。
まとまった金額を咄嗟に工面するのは難しいですが、教育費のピークとなる大学入学までは17年の余裕があるので、子供が小さいうちから積み立てておけば、月々の負担額は小さくなります。
生まれてすぐに用意するのは気が早いと感じられるかもしれませんが、未就学児や幼稚園児のうちは出費が少ないので、早い段階でコツコツ貯める習慣を身につけておきましょう。
積み立てのほかにも、0歳から中学卒業まで支給される「児童手当」をそのまま大学資金として貯蓄するのも1つの手段です。
一般的に児童手当をすべて貯蓄できれば、200万円ほどのまとまった金額になります。
入学費用や授業料の支払いをシミュレーションしながら、子供が生まれてからすぐにコツコツ貯蓄をするのがよいでしょう。
教育費は公立・私立や専門学校・短大・4年制大学に進学させるかどうかによって、用意しておく金額が大きく異なります。
そのため、まずは子供の進路を具体的に考えておくことが大切です。
教育費を貯める方法
それでは、教育費はどのように貯めればよいのでしょうか。
教育費を貯める方法はいくつか存在しますが、その中でも主要な2つの方法を紹介します。
1.定期預金や積立定期預金をする
教育費を貯める方法としてもっとも手堅いのは、定期預金や積立定期預金でしょう。
どちらも解約しない限り簡単には引き出せないため、貯金をつい崩してしまうという方でも比較的お金を貯めやすい方法です。
ただし低金利が続いている近年では、100万円を預けても1年で200円程度しか利息がつきません(利息が年0.025%の場合)。
株式・債券などの投資と比べると金利は低いものの、確実にコツコツお金を貯めたいのであれば有効な方法といえます。
2.学資保険に加入する
教育費を貯める方法として、とりあえず学資保険を選択する方もいるでしょう。
学資保険とは、子供の教育費を準備するために加入する貯蓄型の保険のことです。
保険料を支払い続けることで将来の学費を準備する貯蓄方法という点では「定期預金」や「積立定期預金」と似ていますが、学資保険には「保険料払込免除特約」があり、保険料を支払っている保護者(契約者)が亡くなった場合は、以降の支払いが免除され、満期には契約した時点の満期保険金を受け取れるのです。
ただし、急にまとまったお金が必要になるなどの理由で学資保険を途中解約すると、支払った保険料の総額よりも少ない金額しか受け取れません。
学資保険は満期まで解約しないことを前提に利用するものであるため、無理のない範囲で保険料を設定しましょう。
教育費が足りないときの対策

教育費を貯めようと思っていても、貯蓄の開始時期や世帯収入金額、急な出費などで教育費が足りなくなることも十分に考えられます。
万が一教育費が足りないときには、「奨学金」か「教育ローン」のどちらかを検討する必要があるでしょう。
1.奨学金を利用する
奨学金とは、学生本人に教育費を貸す支援制度の1つです。
奨学金には2種類あり、返済が不要な「給付型」と返済が必要な「貸与型」があります。
給付型は返済が必要ないため条件が厳しく、一定の成績水準や世帯収入の条件を満たしていなければ応募資格が得られないため受給者は限られます。給付型の奨学金は国や自治体だけではなく、高校や大学が独自に設けているものもあるので、子供の進路に応じて問い合わせてみるとよいでしょう。
一方、貸与型の奨学金もあり、給付型に比べるとハードルの低い条件で応募可能です。
利子が発生する有無があり、無利子のものは有利子に比べて厳しい応募条件があります。
奨学金は子供が多額のお金を借り、本人が返していかなければならないため、奨学金を受けるかどうかは子供としっかり話し合うことが大切です。
2.教育ローンを利用する
もし「子供に学費の負担をかけたくない」という場合は、教育ローンを活用するという選択肢もあります。
利子はつきますが、カードローンで借り入れをするよりも低金利です。
また、就学にかかるものであれば入学金・授業料だけではなく、引越費用や下宿費用として利用しても問題はないため、資金使途が奨学金よりも幅広いという特徴があります。
教育ローンは国や民間金融機関が提供していますが、国のほうが審査は厳しく審査期間も長くなるため、教育ローンを検討している場合は早めに審査を申し込むのがよいでしょう。
また、教育ローンは日本学生支援機構の奨学金と一緒に申し込みができます。しかし、併用すると支払い額が膨らんで返済が難しくなってしまう可能性が高くなってしまうため、利用用途に応じて奨学金か教育ローンのどちらかを選択することをおすすめします。
老後のことも考えておく
教育費を貯めるうえで悩みの種となるのが、最低でも1,000万円は必要である「教育費」と自分たちの「老後資金」の準備を両立させなければならないという点です。
「子供のために」と無理をして教育費を工面すると、自分に万が一のことがあった場合やリタイアした場合に十分な貯蓄ができなくなるため、結果的に老後の資金を子供に頼ってしまうという本末転倒な事態に陥ります。
今の子育て世代は公的年金だけでは十分といえないため、教育費に気を配りながらもリタイア後の生活費を工面する必要があるのです。
子供のためを思って教育費を捻出したのに、かえって子供に迷惑をかける結果になってしまうこともあります。
そういった事態を回避するためにも、早い時期から貯蓄を開始したり、返済可能な範囲で奨学金や教育ローンを利用することが大切です。
教育費の目安を立てておくと不安が減る
出産を控えている、あるいは子供がまだ小さいご家庭だと、子育てにかかる出費には見当がつかず漠然とした不安を抱えている方も多くいらっしゃるでしょう。
しかし、子供のためにコツコツ貯めておくべき資金のうち「教育費」は、子供の年齢から教育費の目安と期間がおおよそ想定できる費用であり、目標を定めやすい費用といえます。
必要な金額がわかれば、今やるべきことが見えてきます。
漠然と抱えている不安を具体的な金額にして向きあってみることで、不安は小さくなります。
貯蓄だけで資金の準備ができるか不安な方は、奨学金の活用ができないかを確認しつつ、定期預金や学資保険などの利用も検討しましょう。
「教育費はどれくらい必要なのか?」や「効率よく資金を用意したい」とお考えの方は、お金の専門家であるファイナンシャル・プランナー(FP)に教育資金の不安を相談してみるのも1つの方法です。
ニッセンライフのFPナビでは、何度でも無料で相談できるサービスを実施中。
子供が小さくて外出が難しい場合はご自宅までお伺いすることも可能で、FP事務所やカフェなどでの相談も承っております。
教育費に不安をお持ちの方は、FPナビの「教育資金はファイナンシャル・プランナーにお任せ!」をご覧のうえ、ぜひご相談ください。
※この記事は2022年2月時点の法律・情報に基づき作成しているため、将来、法律・情報・税制等が変更される可能性があります。
出典
「令和3年度 教育費負担の実態調査結果」(日本政策金融公庫)
https://www.jfc.go.jp/n/findings/pdf/kyouikuhi_chousa_k_r03.pdf
「平成30年度 子供の学習費調査の結果について」(文部科学省)
https://www.mext.go.jp/content/20191212-mxt_chousa01-000003123_01.pdf





