教育費に関する特選記事
【2020年大学無償化】対象者は一部、完全無料ではない大学無償化の内容と注意点(8)

なにかと費用がかかる大学費用が無償になるなんて、とてもありがたい話ですよね。
しかしこの無償化、対象になるのはごく一部の低所得世帯だけで、「無償」の範囲も限定的なので注意が必要です。
当記事では、
- 大学費用無償化の対象者
- 無償化の具体的な内容
- 大学費用無償化の注意点
などを細かく解説していきます。
大学進学の予定がある人、将来的に大学進学を考えている人はぜひ、参考にしてください。
■2020年度開始!大学無償化(高等教育無償化)とは
2020年度に開始する大学無償化(高等教育無償化)とは、
- 経済的な理由で高等教育を受けられない学生を支援し、社会で自立して活躍できる人材を育てること
- 安心して子育てできる環境を整備し、教育費の負担を気にして子どもを作らない家庭を減らすこと
この2つを目的とした政策です。
2019年度から実施される「幼児教育の無償化(幼稚園や保育園利用料の無償化)」と合わせた少子化対策のひとつで、共に2019年度の消費税増税による財源を活用して実施される予定です。
「幼児教育の無償化」との大きな違いとして、 高等教育の無償化には所得制限があります。
制度の目的が「低所得世帯の子どもにも大学などで学ぶ機会を与えること」なので、対象になるのはあくまで一部の低所得世帯だけなのです。
出典:「高等教育無償化の制度の具体化に向けた方針の概要」(文部科学省)
■大学無償化(高等教育無償化)の対象者
大学無償化の対象になるのは、
- 住民税非課税世帯の学生
- 住民税非課税世帯に準ずる世帯の学生
で、所得基準の目安は世帯年収380万円以下です。
【所得基準の目安】 両親、本人、中学生の家族4人世帯(世帯主は会社員)の場合
- 年収270万円以下→住民税非課税世帯(支援額は満額)
- 年収300万円以下→住民税非課税世帯に準ずる世帯(支援額は3分の2)
- 年収380万円以下→住民税非課税世帯に準ずる世帯(支援額は3分の1)
実際に住民税非課税世帯になる要件は家族構成や年収、自治体の条例によっても変わってきます。
自分の世帯が対象になるかどうか気になる場合は、お住まいの自治体で詳しい非課税基準を確認するようにしてください。
出典:「高等教育無償化の制度の具体化に向けた方針の概要」(文部科学省)
■大学無償化(高等教育無償化)の内容
大学無償化のおもな内容は、
- 授業料や入学金が年28万円~70万円を上限に減免される
- 生活費などに使える奨学金が年35万円~90万円まで支給される
となっています。
詳しい詳細は以下をご覧ください。
▼大学無償化(高等教育無償化)の内容▼
| 対象になる世帯 |
で、いずれも明確な進路意識や学びの姿勢がある学生が対象。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 対象になる学校 | 大学・短期大学・高等専門学校・専門学校 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 無償化の内容① 授業料等減免制度の創設
| 大学ごとに決まった上限額まで授業料が減免される。 【大学ごとの上限額(年額)】
(国公立) 入学金・授業料ともに、国立の学校種ごとの標準額までを減免。つまり入学金・授業料はほぼ全額免除になる。 (私立) 入学金は、私立の入学金の平均額までを減免。 授業料は、国立大学の標準額に各私立学校の平均授業料をふまえた額と国立大学の標準額との差額の2分の1を加算した額までを減免。つまり、入学金と授業料の7割程度まで免除される。 ※上記は住民税非課税世帯の上限額となる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 無償化の内容② 給付型奨学金の支給の拡充
| 日本学生支援機構の給付型奨学金が国公立・私立種別や自宅外通学の有無に応じて決まった上限額まで支給される。 【大学ごとの上限額(年額)】
※高等専門学校の学生は、学生生活費の実態に応じて、大学生の5割~7割の程度の額を措置。 ※上記は住民税非課税世帯の上限額となる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
出典:「高等教育無償化の制度の具体化に向けた方針の概要」(文部科学省)
大学無償化では、大学の授業料負担が大きく軽減され、生活費などに使える奨学金が支給されるのが大きな特徴です。
ただ、大学にかかる費用は授業料以外にも施設設備費や実験実習費などがありますし、家庭学習や通学にかかる費用なども必要になってきます。
無償化という名前は付いていますが、無償になるのはあくまで学費の一部であり、大学費用すべてが無料になるわけではないのです。
無償化の対象世帯になっても、大学生活にかかるすべての費用を賄えるわけではないことを覚えておきましょう。
■2019年 大学無償化の注意点
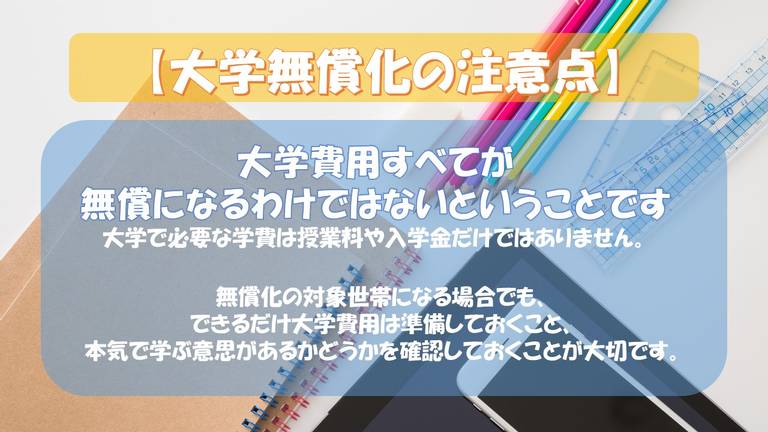
今までお話してきた内容をふまえて、大学無償化の注意点を以下にまとめました。
【大学無償化の注意点】
- 所得制限があるため、対象になるのは一部の低所得世帯のみ
- 大学費用すべてが無償になるわけではない
- 国公立大学は実質全額免除(授業料および入学金)だが、私立大学は一部免除となる
- 進学前も進学後も、個人要件(学びに対する意欲や学習状況など)を満たさなければ無償化を受けられない
- 進学後に退学・停学・習得単位数の不足などがあると支給は直ちに打ち切りになる
特に重要なポイントは、大学費用すべてが無償になるわけではないということです。 大学で必要な学費は授業料や入学金だけではありません。
給付型奨学金は最高額90万円のため、通学費や自宅学習費など4年間の学生生活すべてにかかる費用を賄うのは難しいでしょう。
また、学費の不足を補うためにバイトをして出席単位数が足りなくなれば支給が打ち切りになる可能性もあります。
無償化の対象世帯になる場合でも、できるだけ大学費用は準備しておくこと、本気で学ぶ意思があるかどうかを確認しておくことが大切です。
■2019年 大学無償化 まとめ
大学無償化(高等教育無償化)は、低所得世帯の学費を軽減してくれるありがたい制度です。
しかし、無償化の対象者も無償化になる学費も限られた範囲だけです。大学にかかるすべての費用負担がなくなるわけではありません。
進学後の学習状況が思わしくなければ支援が打ち切りになる可能性もあり、そもそも進学する本人に学習意欲がなければいけません。
大学無償化の対象世帯になる場合も、ならない場合も、大学進学にはさまざまな費用がかかることを念頭におき、そもそも大学で何を学びたいのか、学びの意欲や進学の目的を明確にすることが大切です。
※この記事は2019年6月時点の法律・情報にもとづき作成しているため、将来、法律・情報・税制等が変更される可能性があります。





