家計
【税理士監修記事】iDeCoで保育料はいくら、いつから安くなる?共働き世帯必見のiDeCo活用術

「iDeCo で保育料を安くできると聞いたけど、いくら安くなるの?」
「保育料対策で iDeCo を掛け始めたけど、いつから保育料が変わるの?」
iDeCo で保育料を安くしたいと考え、上記のような疑問を持つ共働き世帯は多いと思います。
とくに 3 歳未満児は保育料が高いうえに、保育・幼児教育無償化の対象外です※。
保育料が家計に与える影響は大きいでしょう。
そこで当記事では、iDeCo で保育料が安くなる仕組みから保育料の計算例まで、わかりやすく解説していきます。
「iDeCo で保育料はいくら、いつから安くなるの?」と疑問に思っている方は、参考になさってください。
※ 住民税非課税世帯を除く
■iDeCo で保育料を安くできる、所得控除の仕組みとは
そもそも何故、iDeCo を利用すると保育料が安くなるのでしょうか。
それは認可保育園や認定子ども園※1 などの保育料を決める「市民税所得割額※2」を、iDeCo の所得控除によって低くできるからです。
※1 児童福祉法の名称は「保育所」ですが当記事では通称名の「保育園」「保育園代」を利用しています。なお当記事で記載している「保育園」は、おもに認可保育所と認定子ども園を指しています
※2 当記事では市町村民税・特別区民税あわせて「市民税」と表現しています。
・保育料決定に用いられる市民税所得割額=課税所得金額(所得金額-各種所得控除)×税率(6%)1-調整控除額
※ 保育料算定で用いられる市民税所得割額の税率は、特例として 6%になっています。ただし名古屋市など、一部自治体では 6%ではない場合もあるのでご注意ください。
※ 保育料を算定する際、ふるさと納税や寄付型クラウドファンディングの寄付金税額控除、住宅ローン利用者の住宅借入金等特別税額控除、配当控除など、一部の税額控除は適用されないので、ご注意ください。
上記の計算式を見てもわかるとおり、保育料を決める重要な要素である市民税所得割額は課税所得金額、つまり個人の収入の多寡で決まります。
しかし iDeCo を利用すれば、積み立てた掛金を全額所得から控除できます。
収入が多い(所得が多い)方でも、iDeCo で積み立てをすればその分課税所得金額を減らし、市民税所得割額も低くできるというわけなのです。
ただし市民税所得割額を低くするだけでは、保育料を安くできるかどうかはわかりません。
認可保育園などの保育料は、各自治体独自で設けられている市民税所得割額の階層区分によって決まるからです。
保育料を安くするためには市民税所得割額を低くし、なおかつ自治体の保育料階層区分を下げる必要があるのです。
iDeCo を利用すれば、100%保育料を安くできるというわけではないので注意してください。
世帯の階層区分や市民税所得割額を確認する方法
iDeCo で保育料を安くするためには、各世帯の保育料階層区分と市民税所得割額を知っておく必要があります。
毎年4月と9月、自宅に送付される「保育料決定通知書(利用者負担額決定通知書と呼ぶ場合も)」に、「階層区分」が記載されています。
<会社員の場合> 毎年5月~6月ごろ、会社で配られる「市民税・県民税特別徴収税額の決定(変更)通知書」の「市民税」箇所に、「所得割額」が記載されています。
<個人事業主・自営業者の場合> 毎年6月ごろ、自宅に送付される「市民税・県民税税額決定・納税通知書」の「市民税」箇所に、「所得割額」が記載されています。
市民税所得割額は、各世帯の収入や所得控除の状況により異なります。
たとえ同じ世帯収入でも、家族構成や所得控除の状況が違えば所得割額は大きく変わるのです。
そのため保育料の計算をする際は、必ず各世帯の所得割額を確認するようにしてくださいね。
■iDeCo の保育料計算例!保育料はいくら安くなる?

ここでは実際に、iDeCo をいくら掛ければ保育料がいくら安くできるのか、具体的な保育料計算例をご紹介します。
東京都でも人口の多い世田谷区を例に、夫婦で iDeCo を毎月 3 万円掛けたら保育料がどう変わるのかを計算しました。
・モデル世帯(夫婦共働き+1歳児1人):世帯の市民税所得割額30万円/階層区分D14・現在の保育料(3歳未満児クラス/階層区分D14): 月額4万7,800円/年額57万3,600円
・iDeCoの掛金額:夫婦で月額3万円/年額36万円・iDeCoの所得控除額:36万円×税率6%=2万1,600円・iDeCo利用後の市民税所得割額:30万円-2万1,600円=27万8,400円・iDeCo利用後の保育料(3歳未満児クラス/階層区分D12) 月額4万2,800円/年額51万3,600円
世田谷区保育料の出典:「認可保育園等保育料改定額(保育標準時間)」(世田谷区) https://www.city.setagaya.lg.jp/theme/006/001/002/d00005744.html
世田谷区の場合、月に 3 万円掛けて月額 5,000 円、年間では 6 万円も保育料を安くできました。
iDeCo で老後への積み立てをしつつ、月に 5,000 円も節約できるのは大きな魅力ですね。
ただ上記は、比較的階層区分が細かい世田谷区の計算例です。
他の自治体ではどの程度の軽減額になるのか、ならないのか?を見てみましょう。
次は全国の主要都市の中でも、保育料が高いと言われる京都府京都市を例に計算しました。
・モデル世帯(夫婦共働き+1歳児1人):世帯の市民税所得割額30万円/階層区分19階層・現在の保育料(3歳未満児クラス/階層区分19): 月額5万1,600円/年額61万9,200円
・iDeCoの掛金額:夫婦で月額3万円/年額36万円・iDeCoの所得控除額:36万円×税率6%=2万1,600円・iDeCo利用後の市民税所得割額:30万円-2万1,600円=27万8,400円・iDeCo利用後の保育料(3歳未満児クラス/階層区分19) 月額5万1,600円/年額61万9,200円
京都府京都市保育料の出典:「令和2年度版 利用者負担額(保育料)に関する御案内」(京都市) https://www.city.kyoto.lg.jp/hagukumi/cmsfiles/contents/0000178/178518/goannnai.pdf
なんと京都府京都市の場合、月に 3 万円掛けるだけでは階層区分が変わらず、保育料も変わらないという結果になりました。
このように保育料を安くできる iDeCo の掛金額は、保育園がある自治体や自身が属している階層区分によって大きく異なります。
iDeCo で保育料を安くすることを考えている方は、この点に留意して掛金額を設定するようにしてください。
■iDeCo で保育料が変わるタイミングは翌年の 9 月
iDeCo で実際の保育料が安くなるのはいつからなのでしょうか。
認可保育園や認定子ども園などで保育料が見直しされるのは、毎年 4 月と 9 月です。
このうち 4 月は子どもの年齢による見直しで、9 月が市民税所得割額の年度変更による見直しとなっています。
くわしい見直しタイミングは、以下の表をご覧ください。
<保育料の見直し時期>
| 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | |
| 9月~翌年3月 | 4月~8月 | 9月~翌年3月 | 4月~8月 |
| 2020年度の市民税所得割額 (つまり2019年の所得額) で保育料が決定 | 2021年度の市民税所得割額 (つまり2020年の所得額) で保育料が決定 | ||
市民税所得割額は、前年の所得と所得控除額によって決まります。つまり 2020 年中に掛けた iDeCo の所得控除が保育料に反映するのは、2021 年 9 月以降です。このように iDeCo の掛金が保育料に反映されるまでは、ある程度タイムラグがあります。1 年後に無償化の対象になる世帯であれば、焦って iDeCo を掛けてもタイミングが合いません。しかし現時点で 0 歳~ 1 歳児クラスの子どもを持つ世帯であれば、早めに準備することで無償化になる前の保育料を安くできる可能性があります。上記の表を参考に「いつの保育料負担を軽減したいのか」をふまえて、iDeCo の開始時期を検討するようにしてください。なお iDeCo で保育料を安くする場合は「掛金の掛けすぎ」にも気をつけてください。iDeCo は老後資金を立てるための制度なので、原則 60 歳まで引き出しできません。保育料を軽減するためとはいえ、今の生活費や、老後資金より先に必要な教育費を圧迫するような掛金では続けるのが難しくなります。各世帯で無理のない掛金を設定し、保育料を軽減しながら、うまく回る家計を目指しましょう。
■ まとめ
共働き世帯で無償化対象外の世帯は、iDeCo で保育料をいくらか安くできる可能性があります。
iDeCo で保育料を活用するためのポイントは、以下 4 点です。
- 保育料が安くなる仕組みは、iDeCoの所得控除で市民税所得割額を軽減できるから
- 保育料を安くするためには、所得割額の軽減だけではなく保育料の階層区分を下げる必要がある
- 保育料の階層区分は自治体によって異なる。必ず各世帯の階層区分や所得割額を確認しておくこと
- 2020年にiDeCoを掛けても、その控除額が保育料に反映するのは2021年9月以降から。タイムラグを考慮して開始時期を調整しよう
保育料が安くなるかどうかは個々の所得割額、自治体の保育料算定基準によって変わってきます。
また、家計を圧迫しない範囲で掛金を設定することも大切です。
iDeCo で保育料軽減を考えている方は、上記ポイントをふまえたうえで掛金額や開始時期を調整し、老後資金の準備と家計の負担緩和を実現させてくださいね。
この記事の内容は 2020 年 4 月現在の税制に基づいています。
監修者
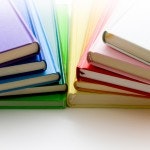
澤村 聡子(税理士)
澤村聡子税理士事務所代表。
【監修者コメント】「iDeCoは、老後資金を準備するには税制面で大変優れた制度である反面、掛けてしまった資金は、原則60歳までは引き出すことができません。 このため将来教育資金や生活資金が不足した時にでも、銀行預金のように簡単に引き出せないデメリットがあります。 保育料の減免だけでなく、将来のご子息の教育や住環境のことなど、幅広いライフプランを慎重に検討してから、掛金を決定してくださいね。」
大学卒業後、都市銀行勤務を経て、税理士試験受験・合格。税理士事務所勤務の後、2009年より現職。
一人一人の納税者の人生に寄り添えるよう、丁寧な対応を心がけています。





