家計
共働きや30代・40代の平均貯金額&貯金額を考えるシンプルなコツを解説

「共働きや30代、40代の世帯は、いくらくらい貯金しているのだろう?」
自分と同じ働き方、年代の世帯貯金額が気になる方は多いと思います。
「よそはよそ、うちはうち」とはわかっていても、同じような世帯構成の人がどれくらい貯金しているのかは、やっぱり気になりますよね。
そこで当記事では、近年増えている「共働き世帯」や働き盛りの「30代・40代の勤労者世帯」の平均貯金額をご案内していきます。
各家庭に適した貯金額をシンプルに考えるコツも、ご紹介します。「世帯の貯金額に不安がある」という方は、参考になさってください。
■各世帯の平均貯金額はいくら?
ここでは総務省の「家計調査」を中心に、共働きや30代・40代世帯の平均貯金額をご案内していきます。
夫婦共働き世帯
30代・40代の勤労者世帯
の平均貯金額はいくらくらいでしょうか?
夫婦共働き世帯の平均貯金額は1,000万円超え!
2018年度の家計調査によれば、夫婦共働き世帯の平均貯金額は1,219万円となっています。
<夫婦共働き世帯 平均貯金額>・データ対象世帯:世帯主の平均年齢48.4歳
| 夫婦共働き世帯全体の平均貯金額(貯蓄総額※)1,219万円(平均年収792万円) | |
|---|---|
| うち、核家族世帯 | 1,162万円(平均年収774万円) |
| 夫婦のみ共働き世帯 | 1,510万円(平均年収748万円) |
| 夫婦と未婚の子ども1人の世帯 | 1,100万円(平均年収789万円) |
| 夫婦と未婚の子ども2人の世帯 | 1,033万円(平均年収784万円) |
※ここでの「平均貯金額」とは、貯蓄性保険や株式などの有価証券を含めた「貯蓄の総額」を指しています
共働き世帯の場合、保険などを含めた貯蓄の総額はどんな家族構成でも1,000万円を超えていますね。
「こんなに貯金できていない!」と焦った方もいるでしょう。
しかし上記データはあくまで夫婦共働き世帯の全体平均値です。
データ対象である世帯主の平均年齢は48.4歳で、世帯の平均年収とともに比較的高めとなっています。
いくら共働きとはいえ、妻がフルタイムの世帯とパートタイムの世帯では収入も違うものです。
また持ち家の有無や住んでいる地域によっても貯金額の傾向は変わってきます。
したがって全体の平均貯金額は、あくまで参考程度に見ておくようにしましょう。
出典:総務省「家計調査」(統計表e-Statより) 共働き世帯の平均貯金額:「2018年度 家計調査<貯蓄・負債編><二人以上の世帯>」より、「第8-9表 妻の就業状態,世帯類型別貯蓄及び負債の1世帯当たり現在高」
30代・40代 勤労者世帯の平均貯金額
30代・40代で2人以上の勤労者世帯の平均貯金額は、30代で631万円、40代で1,012万円となっています。
<30代・40代 2人以上の勤労者世帯 平均貯金額>
| 30代(30-39歳) | 631万円(平均年収632万円) |
| 40代(40-49歳) | 1,012万円(平均年収756万円) |
※ここでの「平均貯金額」とは、貯蓄性保険や株式などの有価証券を含めた「貯蓄の総額」を指しています
※「2人以上の勤労者世帯」とは、世帯主が会社や官公庁などに勤めている一般的な会社員世帯で、2人以上の世帯を指します(世帯主が社長や取締役など会社団体の役員や、個人事業主である世帯は除外)。
年代が違えば貯金額も平均年収も、大きく変わってくるのがわかりますね。
30代は出産・子育て費用や住宅購入費など、出ていくお金が多いうえに年収も低く、なかなか貯金が進まない方が多いのでしょう。
ただ年収が上がりやすく貯金額が多い40代でも、子どもの大学受験、進学などがあれば大幅な貯金減少が予想されます。
いずれの年代にしても、結局貯金額を左右するのは各世帯の家族構成やライフイベントといった個々の状況なのです。
平均貯金額を参考にしつつ、「自分たち家族の貯金適正額はいくらなのか?」を考えることが大切なのではないでしょうか。
出典:総務省「家計調査」(統計表e-Statより)
30代・40代の平均貯金額:「2018年度 家計調査<貯蓄・負債編><二人以上の世帯>」より、「第8-5表 世帯主の年齢階級別貯蓄及び負債の1世帯当たり現在高」
■平均額はあくまで目安 自分たちに必要な貯金額を考えよう
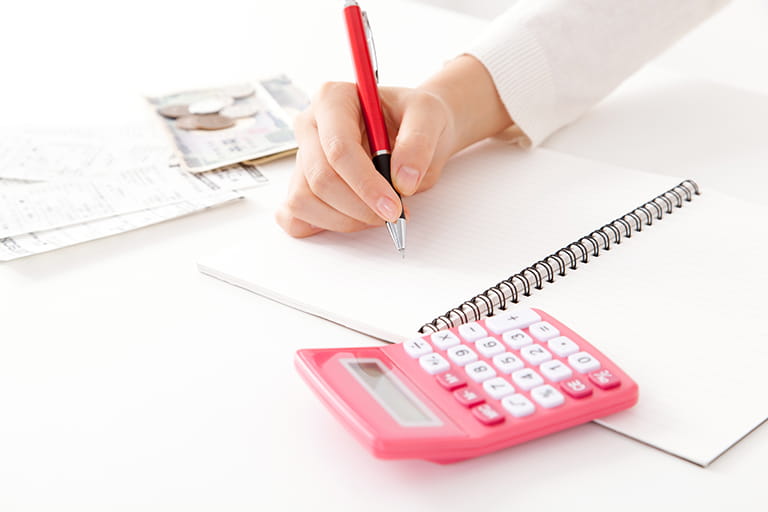
共働き世帯や30代・40代の勤労者世帯の平均貯金額は、あくまでひとつの目安とお伝えしました。
平均データと同じ貯金額でも、住宅ローン残高が1,000万円の世帯もあれば、住宅ローンを完済している世帯もあります。
同じ貯金額であっても安心ということはなく、結局は各家庭によって必要な貯金額は変わってくるのです。
ここからは平均貯金額を参考にしながら、自分たち家族の状況に見合った必要貯金額を考えるようにしましょう。
■シンプルに必要貯金額を考える4つのコツ
共働き世帯も30代~40代の働き盛りの世帯も、「自分の家庭では今、いくら貯金すべき?」を考えるようにしましょう。
そのためには、「必要貯金額の計算には、ライフプランシミュレーションが必須」とお伝えしたいところです。
しかしいきなりライフプランシミュレーションと言われてもぴんとこないし、正直面倒くさいと思う方が多いですよね。
そこでここでは、
- 自分の家庭では今、いくらくらい貯金すべき?
というざっくりした必要貯金額を、シンプルに考えるコツを4つ、ご案内します。
「簡単に必要貯金額を計算したい」という方は、参考になさってください。
コツ①最低限の臨時生活資金から貯める
貯金を始めるときは、まず最低限の臨時生活資金から貯めましょう。
貯金の目的は大きく分けて
- 病気やケガで働けないときや、急な冠婚葬祭などに備えた「臨時生活資金」
- 子どもの教育費や定年後の老後資金など、「将来必要な資金」
の2つがあります。
どちらも人生を豊かに、安心して過ごしていくために必要な資金ですが、資金を必要とする時期が違います。
前者は文字どおり臨時の資金なので、いつ使うかわかりません。
しかし後者は子どもの大学進学や定年など、ある程度必要な時期を予測することができます。
そのため貯金をはじめるときは、いつ必要になるかわからない臨時生活資金を貯めてから、将来の貯金を貯めるようにしましょう。
なお臨時生活資金の一般的な目安は、手取り収入の半年~1年間分と言われています。
迷ったら、まずは最低限の半年分の収入を貯金しましょう。
そのうえで出産前は少し多めに貯めておくなど、各世帯の事情を考慮しながら貯金額を調整するようにしてください。
コツ②子どもの大学費用をいつまでに、いくら貯めるのか決めておく

悩みがちな子どもの教育費では、まず大学費用をいつまでに、いくら貯めるのか先に決めておきます。
具体的には「子どもの大学資金は一人あたり500万円用意することとし、高校3年生の春までに貯金する」というイメージです。
目標金額と貯金の期限を決めておけば、そこに向かって毎月いくら貯めればよいのか計算しやすくなります。
ざっくりした目標貯金額を決めておくべき理由は、
- 教育費は家計の中でも青天井になりやすいから
- 大学費用は必要な時期が明確で、教育費の中で負担が大きくなりやすいから
親であれば誰しも、大切なわが子の将来を左右する教育にはこだわりたいものです。
しかし残念ながら、どんな家庭でも使えるお金には限りがありますよね。
「教育に良さそう」な費用をあれもこれもと掛けていけば、本当に必要な学費を用意できなくなる可能性があります。
留学や習い事などの「こだわり教育費」をどうするかは、子どもの成長にあわせておいおい考えましょう。
まずは最低限必要な学校の費用、その中でもインパクトが大きい大学費用の貯金を優先してください。
大学費用は国公立であれば500万円程度、私立であれば700万円~800万円程度の学費がかかると言われています。
参考:「教育費の総額はどれくらい?学校別・進路別にかかる教育費まとめ!」
こうしたデータを元に、各家庭で大学費用をいくら、いつまでに貯金で用意するのかを決めてください。
将来、子どもの進路がどうなるか、本当に必要な教育費はいくらかは、誰にもわかりません。
将来の予測をあれこれする前に、まずは絶対に必要な資金の準備を始めることが大切です。
教育費には“正解”がなく青天井になりやすいからこそ、まず最低限必要な資金を貯めはじめることをおすすめします。
コツ③住宅ローンは定年前に繰り上げ返済をしておく

持ち家がある世帯の場合は、定年までに住宅ローン完済を目指し、定期的に繰り上げ返済できる貯金を用意しておきましょう。
繰り上げ返済用の貯金は、定年時期にいくらローン残債が残るかを確認して設定します。
「定年時期のローン残債が1,000万円程度で、定年まであと20年ある」という方は、まず5年で250万円貯める計画をたてましょう。
繰り上げ返済はこまめにすればするほど利息の減りが早くなるので、短い期間でちょこちょこ貯金をして返済するのがおすすめです。
35年返済のローンを組み、退職金を繰り上げ返済に充てるつもりの方もいるでしょう。
しかしせっかくの退職金をローン完済に充ててしまえば、老後資金の大切な原資がなくなります。
「退職後も働くつもりだから、ローンさえなければなんとかなる」と思うかもしれません。
しかし老後に企業の再雇用制度を利用したとしても、現役時代と比べて収入は大幅に減少します。
またご自身や配偶者が、問題なく働ける健康状態がいつまで続くかはわかりません。
定年後は収入減少の可能性だけではなく、健康状態の不安が出てくる時期でもあるのです。
こうした不測の事態に対処し、少しでも不安が少ない老後生活を送るためにも、まとまった退職金は必要です。
ただでさえ公的年金の受給額に大きな期待ができない中、老後生活の大切な原資になる退職金には手をつけないようにしましょう。
コツ④老後のもらえるお金と使うお金を計算する
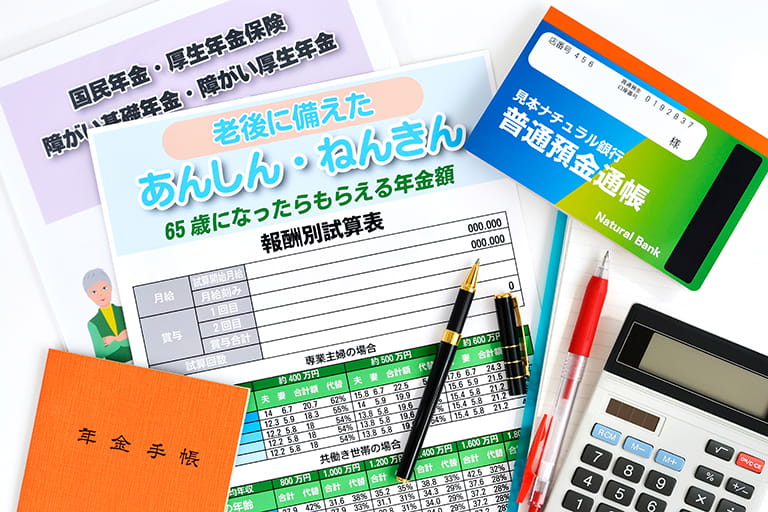
老後生活に必要な貯金額は、老後にもらえるお金から使うお金を差し引いて計算します。
<老後にもらえるお金>
- 公的年金
- 退職金など
→「ねんきん定期便」などを参考に合計額を計算してください
<老後に使うお金>
- 老後に必要な生活費
→「現在かかっている生活費の何割で生活するか」を決めて毎月の生活費を計算し、老後の年数を掛け合わせて合計額を計算してください
老後の生活費の考え方として、現役時代の6割~7割程度の生活費に設定するのが一般的と言われています。
ただ老後の生活水準をどう変えるかは、各家庭で意見がわかれるところですよね。
悩んだらまずは一般的な6割の生活費を設定して計算し、「一般的にはどれくらいの貯金額が必要か」を確認してみてください。
老後生活は長く、いくら必要かで悩む方は多いですよね。
ただ老後生活が始まるまでには、ある程度準備期間があります。
まずはいくらくらい用意しておくべきか大体の目安をざっくりつかんで貯金をはじめ、夫婦で老後の生活を話し合いつつ、必要貯金額を調整していけばよいのです。
少しでも早く貯金をはじめておけばその分、貯金額の調整も変更もしやすくなりますよ。
■まとめ
夫婦共働きも30代も40代も、働き盛りの世帯に必要な貯金額は各家庭の状況により異なります。
各世帯の平均貯金額はあくまで参考程度にとらえ、まずは各家庭で「大体いくらくらい貯金するべきか」を考えるようにしてください。
より細かく、各家庭に適した貯金額を計算するにはファイナンシャル・プランナーなど専門家に相談し、ライフプランシミュレーションを作成するのがおすすめです。
ただ一番大切なのは、ざっくりでもいいので必要貯金額を把握して、貯金という行動をはじめることです。
ご紹介した貯金額計算のコツを参考に各家庭でいくら必要か把握し、貯金をはじめてくださいね。
※この記事は2020年7月時点の法律・情報にもとづき作成しているため、将来、法律・情報・税制等が変更される可能性があります。





