教育・子育て
学童にも待機児童!?高すぎる小1の壁…働き方と育児の悩みどころ

保活を乗り越えた共働き夫婦にとって、次なる試練は小1の壁です。年中~年長のお子さんがいる方は、不安を抱えているのではないでしょうか。
小1の壁にはいろいろありますが、多くは学童保育やその待機児童に結び付いています。
最新の学童保育に関する実態、それにまつわる小1の壁について、情報をまとめてみました。
本来子供の小学校入学は喜ばしいこと!不安な気持ちはできるだけ取り除いて、お祝いしてあげたいですね。今からできる対策方法もまとめています。
共働き夫婦を悩ます「小1の壁」とは

小1の壁とは、子供が小学校1年生になったタイミングで、育児と仕事の両立ができなくなる問題のことです。
さまざまな原因が絡み合っているのに、あまり多く知られていません。
小1の壁は、学童保育にまつわる悩みとそれ以外に分類できます。
学童保育にまつわる壁
- 夏休みなどの長期休みは、お弁当を作らないといけない
- 預けられる時間が短い
- 学級閉鎖になると預けられない
- 使用料が高い(運営主体によって金額は違う)
学校保育に関係ない壁
- 参観などの行事が多く、有給が足りない
- PTA活動などが増え忙しい
- 看護休暇や時短制度は就学前までしか使えないことが多い
- 持ち物や宿題のフォローが増えて忙しい
どれも仕事と両立するうえで、高い壁になることばかりです。
もしかすると、育休明けに保育園に預けたときよりも不安になるかもしれません。
保育園で当たり前にしてもらっていたことが、学童保育ではできなくなるのですから当然です。
とくに「学童保育にまつわる壁」は、現在保育園に通っている方にとって難しい問題。
保育園によっては19:30まで延長保育があっても、学童保育は18:00までというところが多いです。
定時で帰っても、お迎えに間に合わないかもしれません。
また保育園には学級閉鎖がありませんでした。もし小学校のクラスで学級閉鎖が起これば、本人に症状がなくても学童保育に行けないのです。その場合、預け先に困ってしまいますよね。
さらに利用料の問題があります。保育園では1日中預かってもらっても、無償化のおかげで少額の負担で済みましたが、学童保育は所得に関係なく一律料金。きょうだい割引がないことも多いです。費用は月額4,000円~10,000円+実費徴収で月額1,000円~2,500円かかることが多く、1か月2万円以上かかるところもあります。
学童保育は保育園と違うので仕方ないものの、連続して通わせる親にとっては大いに戸惑うポイントです。
学童保育にも待機児童がある!?

そんな学童保育ですが、実は入所自体できない可能性があります。
最近話題になっている、学童保育の待機児童問題です。
待機児童数は1.8万人以上
学童保育(放課後児童クラブ)の実施状況調査結果 によると、2020年5月1日時点での学童保育の待機児童は、1万8,789人にのぼります。しかも待機児童の調査をしていない自治体もあるため、実際の数はもっと多いと言われています。
待機児童は年々増加しており、2014年と比べても2倍以上。共働き世代が増えている現代、今後ますます深刻になりそうです。
また優先順位は1年生からなので、2年生になると入所できなくなったという人もいます。保育園の感覚だと、1度入園すれば卒園までお世話になるのが普通ですが、学童保育の場合は違うことがわかります。
小1の壁とは言いますが、小学校低学年共通の壁と言えそうですね。
学童に入れないと…
もし学童保育に入れないとなれば、何が起こるのでしょうか。
入学したばかりの1年生は、午前帰りが続きます。2年生以上でも15時前後には帰宅するでしょう。しかし会社の時短制度は終わっているため、子供は家で1人になります。
さらに学校の夏休み冬休み春休みは、一日中ずっと家にいます。
子供に合わせて休みを取れば有給が足りず、かと言って1人で留守番させるには、まだまだ心配ですよね。テレビやゲームで1人遊びもできる時代ですが、毎日の数時間をそのように過ごさせるには、抵抗のある親が多いものです。不慮の事故や犯罪に巻き込まれる可能性もあり、このような不安から退職せざるを得ないケースがあるのです。
せっかく保育園に預けて仕事を続けられたのに、小学校入学のタイミングでやめないといけない…あまり知られていない現状ですが、家計にもキャリアにも、深刻な問題です。
今からできる!小1の壁対策5選
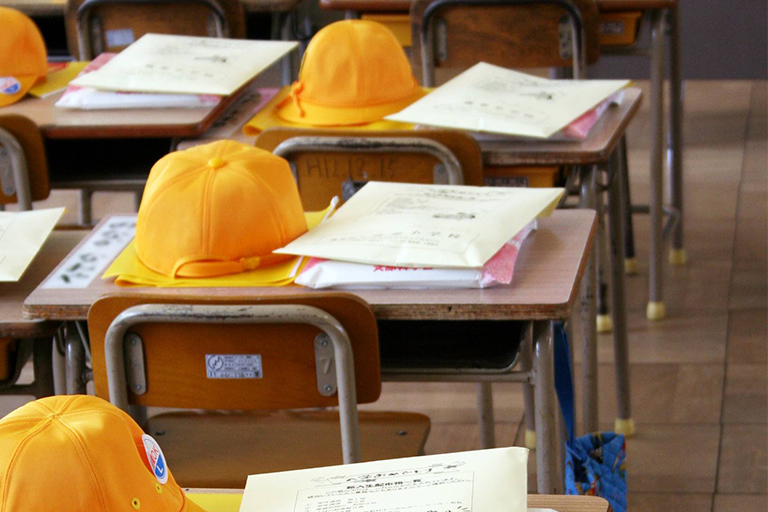
退職するしかない…そう決断する前に、今からできることを少しずつはじめてみましょう。
先輩が行ってきた方法を5例ご紹介します。
①民間の学童を探す
学童保育は公設だけでなく、さまざまな形態があります。
学童保育は保育園と違うので仕方ないものの、連続して通わせる親にとっては大いに戸惑うポイントです。
もしかすると、対象の地域内に小規模で運営している民間の学童保育、放課後デイサービスなどがあるかもしれません。
保育園の先生やママ友から情報を集めてみましょう。
②シッターやファミリーサポートサービスを利用する
学童保育に入れない場合、他の有料サービスを探してみましょう。
シッターやファミリーサポートサービスなどを利用できる場合があります。ただし利用料は、学童保育料よりも高くなるでしょう。費用の高さで諦めるべきか、それとも仕事を続けるために利用するべきか。こちらについては次の「学童保育や代替えサービス、その価値はある?」「学童保育や代替えサービス、その価値はある?」でもう少しくわしく考えていきます。
③近くの習い事や児童館に通わせる
家の近くに習い事教室や児童館 がある場合、そちらに毎日通わせている先輩ママもいます。児童館は閉館時間が短かったり休館の曜日が決まっていたりするので、習い事と合わせて週5日の予定を立てているようです。
入退室したときに、親にメールが来るサービスのある習い事だと安心ですね。
ただし学校から直接行けないことがほとんどなので、1人で通えることが条件。習い事代もかかりますし、預かり事業ではないので希望通りにいかないことも想定しなければなりません。
④働き方を変える
思い切って働き方を変えるのも選択肢の1つです。学童保育でも、保育園のように点数制で審査しているところがあります。
もし現在パートとして働いていて、審査基準に勤務時間や勤務体系があるのなら、正社員やフルタイム勤務を目指すことで解決できるかもしれません。
逆に現在正社員やフルタイム勤務で、学童保育に入れなかったりお迎えの時間に間に合わなかったりするなら、時短パートになるのも1つの選択肢となります。
⑤会社の制度に変更がないか確認
会社の就業規則もしっかり確認しましょう。実は変更されたのに気づいていないことはないでしょうか。実は⼦の看護休暇制度が2021年1月に変更になり、時間単位で取得できるようになりました。こうした国の動きを受けて、会社独自で制度を拡充したケースがあります。直近では時短勤務をとれる期間が就学後まで延びたり、テレワーク体制が整ったりした会社がありました。
ママだけでなくパパも、会社の人事や総務担当に確認してみましょう。
学童保育や代替えサービス、その価値はある?

小1の壁を乗り切る手段をいくつかご紹介しましたが、「そもそも越えないといけない壁なのか?」「退職する方がいい気がしてきた」と思えてくる瞬間もあると思います。
とくにサービス利用料(習い事代など)がかかることや、子供を1人にさせる不安を考えると、そのような考えに陥るのも仕方ありません。
しかし、すぐに「退職」という選択肢をとるのではなく、じっくりと向き合ってほしいという思いでこの記事を書いています。
なぜなら、保活を乗り越え築いてきたキャリアがあるからです。今後のライフプランを考えたとき、天秤にかけるものは見極めないといけません。学童保育やシッター料が高くても、長い目でみれば働いている方がいいこともあります。
もちろん母親の働き方は家庭によりますし、専業主婦として育児に向き合うのも1つの形ですよね。家族の形はそれぞれです。
しかし、もし目の前の問題だけを見て働き方を変えてしまうと、後悔してしまうこともあります。
しっかりライフプランをたてて、情報も仕入れた上で話し合いましょう。
学童保育の問題は地域によってことなるため、自治体に合わせた情報収集が必要です。一方ライフプランやキャリアについては、家計のプロであるファイナンシャル・プランナーに相談できます。
目の前の問題で不安が大きいとは思いますが、本当に退職しても大丈夫かどうかはじっくり考えましょう。
小1の壁と学童保育についてのまとめ
共働き夫婦が悩みやすい小1の壁についてお伝えしました。学童保育にまつわるものが多く、退職も視野に入れないといけない現状がわかりましたね。
- 学童保育には保育園のような手厚いサービスがなく、仕事と両立しにくい
- そもそも学童保育には待機児童があり、入れない可能性もあるので対策が必要
- すぐにキャリアをあきらめるのではなく、ライフプランを総合的に考えることが必要
小学校入学は、お子さんの大切なライフイベントです。親にとっても成長の感じられる大切な瞬間。心からお祝いしてあげたいものです。
そのためにも不安を解消できるよう、今日からでも対策を考えましょう。
楽しい小学校生活のスタートがきれるよう、心から応援しています。
出典
学童保育(放課後児童クラブ)の実施状況調査結果について「全国学童保育連絡協議会」
http://www2s.biglobe.ne.jp/Gakudou/pressrelease20201209.R1.pdf
令和元年(2019年) 放課後児童健全育成事業(放課後児童クラブ)の実施状況(令和元年(2019年)5月1日現在)「厚生労働省」
https://www.mhlw.go.jp/content/11906000/000580501.pdf
執筆者
ニッセンライフ編集部
ニッセンライフの編集部に所属する、働く双子ママ。
「遊びたい盛り、食べたい盛り、論破したい盛り」の双子を育てながら、
子育て世代の心が軽くなるような情報を発信しています。







