教育・子育て
【2021年大学入試】推薦入試は楽?昔とは違う点もあるので要チェック!
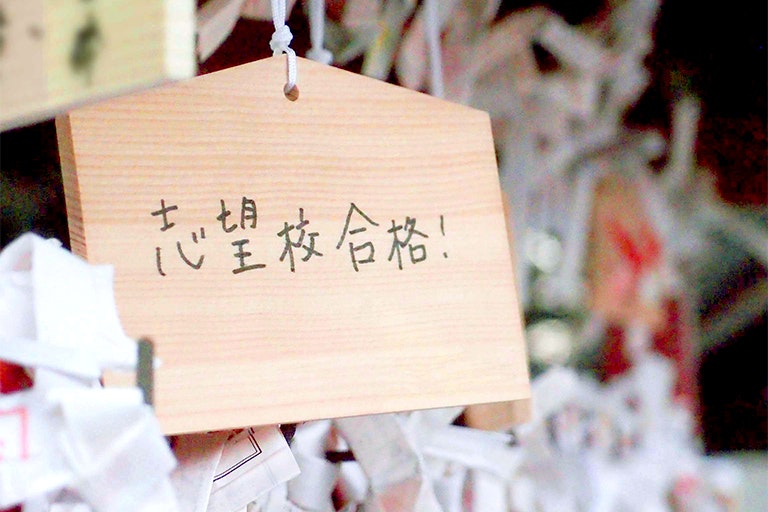
「推薦入試で合格が決まれば楽だから、子供には推薦入試を目指してもらったほうがいいのかな?」
推薦入試を狙ったほうが楽だと考える人もいるかもしれませんが、2021年の推薦入試にはさまざまな変更があり、注意すべき点が増えました。
この記事では以下の内容について詳細を解説していきます。
- 大学推薦入試の概要やスケジュール
- 推薦入試を選ぶメリットデメリット
- 大学進学にかかる教育資金の準備について
子供の大学受験をひかえた親御さんたち、ぜひ参考にしてみてくださいね。
推薦入試の方法にはどんなものがある?スケジュールも説明
子供の将来に影響する一大イベントである「大学入試」。2021年の入試では従来のセンター試験に変わって「大学入学共通テスト」が開始しました。
変更が加わっているのは推薦入試も同様。推薦入試に関しては2020年から従来型の推薦入試が廃止され、新しい制度に移行しています。
2021年の推薦入試の概要について、以下の表にまとめました。
| 推薦入試の種類 | 旧名称 | 実施大学 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 総合型選抜 | AO(アドミッション・オフィス)入試 | 国公立大学 私立大学 | |
| 学校推薦型選抜 | 推薦入試 | 国公立大学 | 「公募制」のみ |
| 私立大学 | 「公募制」と「指定校制」の2種類がある |
それでは「総合型選抜」「学校推薦型選抜」それぞれの特徴や、受験スケジュールについて見ていきましょう。
総合型選抜(旧AO入試)とは
総合型選抜とは、大学側が求める人物像であることを評価基準とする推薦入試の選抜制度。大学と生徒とのマッチングを重視する性質については、旧AO入試と同様です。文部科学省によると、国公立全体の56.9%が総合型選抜を実施しています。
出願時期:9月以降
合格発表時期:11月以降
※ただし「大学入学共通テスト」の受験が必須となっている大学の合格発表は2月。
<総合型選抜の入試の特徴>
- 試験内容は大学によって異なるが、面接・論文・プレゼンテーション・口頭試験などを行う。
- 学校推薦型と異なり、高校校長の推薦が不要である。
- 大学との面接回数が多く、受験期間が長期化する傾向にある。
受験が長期にわたるうえ、試験内容が多彩であることが特徴。目指す大学や専攻に特化した、専門的な対策が必要になります。「どうしてもこの大学がいい、これを専門的に学びたい」という強い目標がある人向けの受験といえるでしょう。
学校推薦型選抜(旧推薦入試)とは
学校推薦型選抜(旧推薦入試)は学力だけでなく、部活動や課外活動での実績や意欲・学生の個性を総合的に評価して選抜する入試方法です。試験資格を得るには、学校長の推薦状が必須になります。
文部科学省によると国公立全大学の96.0%が「学校推薦型選抜」による入試を実施。また令和2年度大学合格者のうち、およそ4割が旧推薦入試によるものです。
学校推薦型選抜には「公募制」と「指定校制」の2種類があります。
- ● 公募制・・・大学が全国から受験を募集する推薦入試の制度。大学が求める出願条件を満たした上で学校長の推薦状さえあればどの学生でも受験でき、募集人数が比較的多い。
- ○ 公募制一般選抜・・・成績基準が設けられることの多い、一般的な選抜制度。募集定員が多いことが特徴。
- ○ 公募制特別推薦選抜・・・部活動や課外活動で優秀な成績を収めた生徒を対象とした選抜制度。いわゆる「スポーツ推薦」。
- ● 指定校制・・・大学側が指定した高校のみが受験資格を得られる。推薦者数が少なく学校内で枠を勝ち取るのが難しいが、推薦状を得ることができれば大学への合格率は高い。
出願:11月以降
合格発表時期:12月以降
※ただし「大学入学共通テスト」の受験が必須となっている大学の合格発表は2月
<学校推薦型選抜の入試の特徴>
- 国立は「公募制」が多く、「指定校制」はほとんど行われていない。
- 学校成績が重視される。高校生活3年間を通した成績の数値が重要になる。
- 書類推薦・面接(集団面接)・小論文などが出題される。
- 原則併願不可で、専願が多い。
学校推薦型選抜は、高校での生活態度や意欲が高く、学校成績のよい生徒が有利な受験方法です。高校生活全体を通して、各科目の平均成績が高い生徒であればチャレンジしてみるとよいでしょう。
総合型選抜・学校推薦型選抜の注意点とメリットデメリット
旧推薦入試やAO入試から変更された内容のうち、注意点として押さえておきたいのが「学力検査」「評定平均審査」が重視されていること。
新制度からは文部科学省の方針で「学生の学力を重視する」方向にシフトしています。その流れを受け「独自の学力試験」や「大学入学共通テスト」の受験が必須になっている大学もあるのです。推薦入試を検討する際は事前に受験する大学の入試要項で、学力試験の有無を確認しておきましょう。
少なくとも「大学入学共通テストを避けたいから」という理由で推薦を選ぶことはオススメできません。上記のとおり、大学入学共通テストの受験が必須となっている大学もあるからです。全体的に学力を重視する試験方式が増えているため、たとえ推薦狙いであっても「試験勉強対策」は必要になるでしょう。
推薦入試を受けるメリット
- たとえ合格できなかったとしても一般選抜があるため、受験の機会が増えることになる。
- 一般選抜と比較して早く結果が出る。
推薦入試は、早い時期に合格がわかることが大きな魅力。早くて12月には結果が出るため、合格すれば数か月間を自由な時間にあてられるのです。
まとまった時間を利用して「自動車免許の取得」や「アルバイト」などを経験するのもいいでしょう。ただし高校の校則によっては、在学中の免許取得やアルバイトを禁じているところもあるため注意。万が一事故を起こしてしまった場合などは、入学取り消しなどにもなりかねませんので慎重に対応しましょう。
推薦入試を受けるデメリット
- 試験対策が多岐にわたるため、対策が難しい。
- 合格できなかった場合に受験費用がかさむ。
デメリットは「軽い気持ちでは受験できない」という点にあります。新制度になって日が浅いため大学ごとの出題傾向がつかみづらく、試験対策が難しいためです。また試験開始が早いのも難しさのひとつ。早め早めの対策が重要になります。
もうひとつのデメリットとして挙げたのが、受験費用についてです。合格できなかった場合、受験費用が余分にかさむことになります。
受験費用は大学や学部によって幅がありますが、国公立が平均1万7,000円程度、私立が平均3万5,000円程度。一般選抜で複数大学受ける場合、これらの金額が受験大学数分加算されることになります。狙った大学を過不足なく受験することが大切になります。
大学入学に向けた教育資金の準備を
近づいてくる大学入学に向け、早めに準備したいのが教育資金。大学受験から大学入学にかけての期間は、まとまった金額の教育費用が必要になるのです。
具体的な金額をお伝えすると、大学入学のために支払った学費の平均は82万8,000円。
内訳は次のとおりです。
- 受験費用31万9,000円
- 大学納付金41万9,000円
- 入学しなかった大学への納付金9万円
大学進学に向けた教育資金は、学資保険で準備している人も多いことでしょう。ただし学資保険は、必要なときに自動的に振り込まれるわけではないことを知っていましたか?
学資保険に加入している人がチェックすべき「満期保険金の受け取り方」を確認してみましょう。
学資保険の満期保険金を受け取るには請求手続きが必要
せっかく学資保険に加入していても、必要なタイミングで保険金が受け取れなくては本来の意味を発揮できません。必要なときに速やかに満期保険金を受け取れるように、学資保険の請求手順をチェックしておきましょう。
- 保険証券で保険期間の満期を確認しておく。
- 満期が近づくと、保険会社から満期の通知が届く。
- 通知内容に基づき、満期保険金の請求手続きをする。
請求のポイントは、保険期間が満期になるタイミングを早い段階でチェックしておくこと。その理由は、満期月によって入試や入学までに保険金の受け取りができないケースがあるからです。
学資保険の満期は「18歳満期」「17歳満期」のように、子供の年齢が基準になります。そのためもし「18歳満期」で契約していた場合、子供の誕生日によっては入学手続きまでに保険金が受け取れない可能性があるのです。
保険が出ると思っていたから現金を用意していない!ということにならないよう、申込前に確認することはもちろん、事前に学資保険の満期を確認しておきましょう。余裕をもったスケジュールで、教育資金の計画を立てると安心です。
推薦入試をする場合に備えて早めに大学入学費の確保を
学資保険に加入していない場合は、貯蓄を取り崩すなど別の方法でまとまった資金を用意する必要があります。大学に合格しても入学金の納付期限を過ぎると合格が取り消されるため、計画的な資金準備は必須です。
入試や合格発表のタイミングが早い推薦入試の場合、一般選抜よりも早い時期から資金が必要になります。
お金を貯めるには時間も必要なので、直前になって慌てることのないよう、お子さまが生まれたときなど、早めに教育資金の確保のため動いておきましょう。
教育資金の準備方法や具体的な家計の相談は、ファイナンシャル・プランナーに相談することをオススメします。
入学金の準備はもちろんのこと、大学生活の4年間は授業料や下宿代など子供の教育資金がもっともかかる時期。さらに子供の独り立ちを見据え、夫婦の老後についても考え始めるタイミングです。
家族の将来を考え、お金のプロであるファイナンシャル・プランナーに悩みや疑問を話してみてくださいね。
⇒教育資金について相談してみる
まとめ
2021年推薦入試の概要や教育資金の準備について、以下のとおりまとめます。
- 総合型選抜は学校長の推薦状が不要で、大学と生徒とのマッチングが評価される試験方法。どうしても行きたい大学や学部がある学生向けの受験方法である。
- 学校推薦型選抜を受けるには学校長の推薦状が必要になるため、学校成績や部活動などで優秀な成績を収めていることが必要になる。
- 推薦入試の大きなメリットは「受験機会が増えること」「合格結果の通知が早いこと」。一方デメリットは「試験対策が難しいこと」「受験費用がかかること」。
- 学資保険で教育資金を準備している場合は、自分で請求手続きすることを忘れずに。また満期がいつかを事前に確認しておくことが大切。
- 教育資金の準備について不安があれば、ファイナンシャル・プランナーに相談するのがオススメ。
情報提供や資金の準備など、親としてできる限りのサポートをして子供を合格に導いてあげたいですね。
とくに教育資金については早めの対策が重要。
不安な場合はファイナンシャル・プランナーの力も借りながら、家族一丸となって大学受験の荒波を乗り切りましょう。
⇒教育資金について相談してみる
※この記事は2021年7月時点の法律・情報に基づき作成しているため、将来、法律・情報・税制等が変更される可能性があります。
執筆者

pomoco
元金融会社勤めのフリーランスライター/2級FP技能士資格保有
FP資格の知識を生かし、金融全般や家計といったジャンルを中心に執筆活動中。
会社員のときに感じていた「ワーママの毎日に楽しい!を増やしたい」というテーマで、日々情報を発信しています。





