教育・子育て
中高一貫教育校とは?塾通いを始める前に知っておきたい概要と受験準備

子どもが小学生になると、中高一貫校への中学受験を考える機会が出てきますよね。
筆者も子どもが来年小学生です。
受験するかどうかはまだわかりませんが、あらゆる選択肢を持っておくために情報収集をしています。
いろいろと調べて気付いたのは、中高一貫教育校に行くなら準備はできる限り早いほうがいいということ。
一般的には小学3年生の3学期から塾通いですが、中学受験の塾通いは子どもにとって大きな負担です。だからこそ塾通いが始まる低学年のころから、ある程度心づもりをしておく必要があると思いました。
この記事では塾通いを始める前に知っておきたい、中学受験の概要や受験準備について親目線で解説します。
「受験をするかどうかはわからないけれど、中高一貫教育や受験がどのようなものか知っておきたい」方は、参考にしてみてください。
中高一貫教育の概要・実施形態
中学校と高校の6年間を通じて、一貫した教育が行われる中高一貫教育。
子どもの個性や創造性を伸ばし、教育の選択肢を広げることを目指して制度化されました。
以降、中高一貫教育を実施する学校は年々増えていて、2019年時点で全国に664校あります※。
中高一貫教育校の良さは、学習指導要領の範囲を越えた教育課程が展開されている点にあります。各学校で独自のカリキュラムがあり、子どもが望めば芸術やスポーツに特化した専門学科に通うことも可能です。進学校であればスピーディに授業が進んでいくため、大学受験も見越した学校教育を期待できるでしょう。
ここでは中高一貫教育制度の実施形態と、一般的な教育の例を解説しています。
※全国に設置されている中学校のうち、中高一貫教育を実施する学校の数。
「学校基本調査-令和元年度結果の概要-」より「表13 中学校の設置者別学校数」を参照(文部科学省)
中高一貫教育の実施形態・教育例
中高一貫教育を実施する学校は、おもに以下3つに分けられます。
| <中高一貫教育の実施形態> | |
|---|---|
| (1)中等教育学校 | 一つの学校として、中学校と高校の教育を一体化させて実施することを目的として設立された学校 |
| (2)併設型 | (1)よりもゆるやかな形態で、高等学校入学試験を行わず、同一の設置者が中学校と高等学校を設置している形態 |
| (3)連携型 | 中学校と高校の設置者が一体になっている(1)や(2)と異なり、中学校と高校の設置者が異なる場合でも連携し、中高一貫教育を実施できるようにした形態。学校によっては、簡便な高等学校入学試験が行われる ※設置者が同一の場合もある |
ただし校風や教育方針は、学校ごとに大きく異なります。
文部科学省がホームページでまとめている、一般的な中高一貫教育校での教育例は以下のとおり。
“(以下引用)
- 普通科タイプ:複数のコースを設け,様々な選択を可能とするものや,比較的小規模の中学校と高等学校が一体化し,幅広い年齢層を通じた生徒間交流により学校の活性化を目指すもの。
- 専門学科タイプ:芸術・スポーツ・伝統文化・外国語等の専門的分野に興味・関心・才能を有する生徒に対し,6年間の計画的・継続的な教育を行うもの。
- 総合学科タイプ:複数の系列を設け,その中から生徒が能力・適性や興味・関心に応じて主体的に選択できるもの。“
引用元:「中高一貫教育Q&A:教育課程・評価に関すること」(文部科学省)
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/ikkan/10/1315807.htm
「今はまだ受験するかどうか決めていない」という家庭もあるでしょう。
しかし事前にある程度概要を把握しておけば、いざ子どもが受験したいとなった時に慌てず行動しやすいです。
中高一貫教育校へ通わせるためには、どのみち子どもに相当な負担を強いることになります。少しでも気になっているのであれば、まずは中高一貫教育について把握しておき、今からできることは何かを考えることが大切です。
⇒教育資金について相談してみる
中高一貫校 私立と公立の違い
中高一貫校にも私立と公立があります。
それぞれのおもな違いは、「学費」と「入試方法」です。以下をご覧ください。
- 学費:地域や学校によって違いはあるが、一般的には公立のほうが学費は安い。公立の場合、義務教育である中学校の授業料は無償で、それ以外の学費も私立より抑えられていることが多い
- 入学方法:公立の中等教育学校・併設型中学校の入学時には学力検査は行われず、各学校独自の「適性検査」が導入されている。私立校では4教科を中心とした「教科試験」が導入されているのが一般的
公立の中高一貫校の学費相場は年間40万円~60万円程度ですが、私立の中高一貫校の学費は100万円~150万円が相場です。
特に私立は小学3年生の3学期から塾通いが始まるため、入学前から数十万単位の支出が発生します。私立に通わせたい場合は、高額になりがちな塾代も含めて家計と教育費の兼ね合いを考えておく必要があるでしょう。
入学方法も、私立と公立では大きな違いがあります。
私立の中学受験の出題範囲は小学校の学習範囲を超えているため、3・4年生のころから塾通いをするのが一般的です。
一方、公立校の適正検査は小学校の学習範囲内で、学力検査はありません。ただし学校ごとに独自の適正検査を実施しているため、公立校独自の受験対策カリキュラムを導入している塾もあります。
学費の安い公立校は、それだけ倍率が高くなりがちです。
学力検査がないといっても簡単に合格できるわけではなく、受験対策のプロである塾の力を借りるのが現実的な受験対策ではないでしょうか。
つまり私立でも公立でも、いずれ塾通いは必要です。
ただし塾のカリキュラム・試験対策が違うため、塾通いする前に私立か公立かは決めておかなければいけません。
中高一貫校に入れるなら小学校低学年から準備が必要

一般的に、子どもを中高一貫校に入れる場合の勉強は、小学3年生の3学期から始まると言われています。
なぜ3年生からかと言うと、大手進学塾の私立中学受験対策コース(小学4年生コース)が3年生の3学期(2月ごろ)に始まるからです。
大手進学塾のカリキュラムから、一般的な中学受験対策コースのスケジュールを以下にまとめました。
<一般的な中学受験対策の塾通いスケジュール>
- 小学4年生コース(小学3年生の3学期スタート):17時~20時ごろまでを週に2・3回
- 小学5年生コース:17時~21時ごろまでを週に4・5回
- 小学6年生コース:17時~22時ごろまでを週に5・6回
この他、夏休みや春休みといった長期休暇時には集中的に受ける講習会が開かれます。小学校から帰宅して学校の宿題を終え、夕方から夜遅くまで塾で勉強。塾がない日は、塾の宿題や予習もしなければなりません。習いごとや友達と遊べる時間は、極端に少なくなります。
これほど過酷なスケジュールを、まだ成長過程にある10歳前後の子どもに課すのが中学受験です。
筆者は中学受験の現実を知り、小学3年生でいきなり塾通いをさせるのは子どもにとって負荷がかかりすぎると思いました。学校や習いごと・友達との遊びが中心の生活から、3年生で急に塾中心の生活にシフトさせるのは、ギャップが大きすぎるからです。
何の準備もなしに急にハードな塾通いをしてしまえば、子どもの気持ちや体力がどこまで続くかわかりません。
そのため、中学受験を少しでも考えているのであれば、低学年のころから学習の土台を作り、親子で心身の準備をしておくことが大切です。
実際に中学受験経験者に話を聞くと、低学年のころから家庭学習をする習慣を作っていました。具体的には、自宅で簡単なドリルを親子でする、本を読む時間を作るなど、学校以外の学習を自然にする環境を作っておくのです。
そうして学習への苦手意識をなくしておけば、いざ塾通いを始めても負担を感じにくくなるのではないでしょうか。
まとめ
子どもを中高一貫教育校に通わせる場合、私立でも公立でも塾通いは必須です。
一般的には小学3年生の3学期から塾通いを始めますが、その段階で急に塾中心の生活にシフトさせるのは大きな負担になります。
中学受験の経験者に話を聞くと、どの家庭でも低学年のころから自宅学習をしていました。
親の視点でも、中高一貫教育校に行くかどうかを決める前に、まずは小さいころから学習の下地を作っておくことが大切だと感じます。
もちろん中高一貫教育校に行くかどうかは、本人の気持ちが何より重要です。
親としてできることは、いざ中学受験をするときのために、ハードな塾通いをこなす体力と気力を付けてあげることではないでしょうか。
⇒教育資金について相談してみる
※この記事は2021年7月時点の法律・情報に基づき作成しているため、将来、法律・情報・税制等が変更される可能性があります。
執筆者
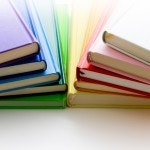
服部 椿
プロフィール:FP分野専門のフリーランスライター。
子育て中のママFPとして、子育て世帯に役立つ家計や投資、お金に関する情報を発信中。
保有資格:2級FP技能士





