家計
遺産相続にも信託が役立つ!葬儀代などを素早く受け取るための準備とは

通常、預貯金等を預けている金融機関の口座名義人が死亡してしまい、金融機関がそれを知ると財産相続トラブルの防止のため、すぐに口座が凍結されてしまいます。凍結されてしまうと、引き出すことも入金することもできません。凍結が解除されるまでには煩雑な手続きが必要で、葬儀費用などすぐに必要となるお金が引き出せず、困ってしまうケースが多くなっています。そういった事態を予防するために人気が高まっているのが、遺言代用信託です。
■死亡時には口座が凍結されてしまう
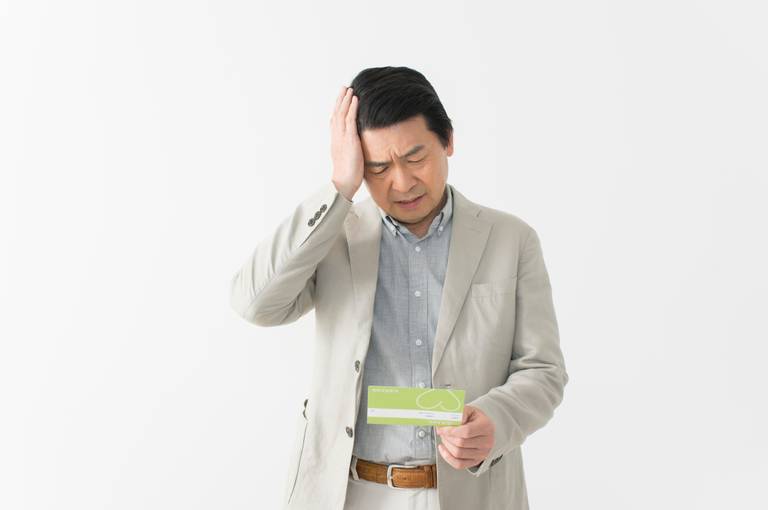
口座の名義人が死亡した場合、口座は凍結され、原則預金を引き出すことができなくなります。
預金は相続開始から遺産分割協議が終了するまで相続人の共有財産となるため、勝手に相続人の1人が預金を引き出すと、遺産相続において大きなトラブルに発展してしまう可能性があります。そのため、財産相続トラブルに巻き込まれないために、金融機関は名義人の死亡を知ると速やかに口座凍結の処置を行います。
そうなると、葬儀費用や当面の生活費、公共料金の引き落としなど、当面の費用に困ってしまうケースが出てきます。口座凍結後であっても、金融機関に相談すればある程度の引き出しには応じてくれますが、受取には戸籍謄本や法定相続人全員の同意書など、いくつもの書類が必要となります。
そうして預金を引き出した後も、財産相続トラブルを防ぐために葬儀費用の領収書などをきっちり保管しておき、不正使用がなかったと証明できるようにしておく必要があります。
■すぐに引き出せる!遺言代用信託とは

口座の名義人が死亡した場合、金融機関から預金を引き出すには煩雑な手続きが必要となり、かなりの困難が伴いますが、そういったときに頼りになるのが「遺言代用信託」といわれるサービスです。
遺言代用信託は、あらかじめ信託銀行などの金融機関に被相続人が法定相続人の中から特定の相続人を指定してお金を預けておき、被相続人が死亡した際に、指定された相続人がすぐにお金を受取できるものです。受取るお金は相続人が相続することが決まっているお金なので財産相続トラブルも防止できますし、受取の手続きに必要なのは死亡診断書や本人確認書類、印鑑といった簡単なものなので、最短で請求当日に相続財産を受取ることができます。専門的知識のある機関に財産の管理や運用を任せることができ、遺言と同じように相続人を指名して相続させることができるため、近年利用件数が大幅に伸びているサービスです。
被相続人が定める受取方には大きく2つの方法があり、大きな金額の一時金を一気に受取る「一時金型」と、一定の期間に分割して受取る「年金型」とに分かれます。一時金型と年金型を併用することも可能です。
遺言代用信託で預けられるのは金銭のみで、不動産などは対象外となっています。また金額にも上限があるため、財産が一定以上ある場合は、遺言代用信託のみで遺産相続を賄うことはできません。
■生命保険との違い
受取人を指定する点では生命保険と似ていますが、遺言代用信託では手数料などがかからない商品が多く(※商品によっては別途信託報酬など手数料がかかる場合もあります)、加入年齢にも制限がないものがほとんどです。
ただし、相続税の非課税枠が存在する生命保険と異なり、遺言代用信託には非課税枠の取り扱いはありません。遺言代用信託で受取った相続財産には相続税が発生するため、注意が必要です。生命保険は節税対策によく利用されますが、遺言代用信託は節税対策というよりも、スムーズな遺産相続のための手段の一つといえるでしょう。
さらに、法定相続人の遺留分についても注意が必要です(※遺留分とは、一定の相続人に対して法律上確保できる一定割合の遺産のことで、遺言などで相続人の遺留分が侵害されるような場合には、受遺者や受贈者に対して遺留分の減殺請求をすることができます)。生命保険では原則として遺留分の減殺請求はできませんが、遺言代用信託では可能となっています。「遺言代用信託で3人いる子どものうち1人だけに全財産を残す」といった遺産相続を行ったとしても、ほかの2人がもし遺留分を請求すれば遺言代用信託から遺留分を分割しなければなりません。法定相続人が複数いる場合には、遺留分のことを考えて信託を利用しましょう。
お金に関する不安・お悩みを解決! ファイナンシャル・プランナーへの相談はこちら





