教育・子育て
奨学金返済に苦しむ若者が増加中。奨学金の真実と学費対策

一般的に「奨学金」といわれるものには、返還が不要な給付奨学金と、返還が必要な貸与奨学金があります。ここでは、奨学金の仕組みと学費対策をご紹介します。
■貸与奨学金の仕組みと特徴
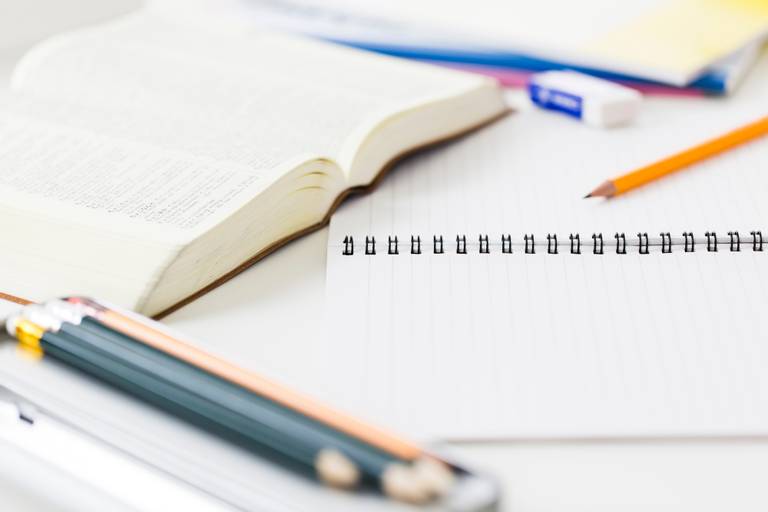
貸与奨学金で最も多く利用されているのが、公的機関である日本学生支援機構(JASSO)の奨学金です。JASSO奨学金は、無利子で貸与される第1種奨学金と、有利子貸与の第2種奨学金とに分かれており、それぞれ家庭の所得や本人の学力などの貸与条件が異なります。文部科学省の調査によると、2014年度には第1種・第2種を合わせ約140万人もの学生がJASSO奨学金を利用しています。
奨学金は在学中毎月一定額振り込まれ、卒業するまでは返還の必要はありません。卒業後、貸与が終了した翌月から数えて7ヶ月目から返還が開始され、奨学金を受け取った学生本人が返還します。返還された奨学金は、次の世代の奨学金として利用される仕組みとなっています。
■奨学金返還に苦しむ若者が増加中

学費負担を軽減する奨学金ですが、労働者福祉中央協議会の調査(2016年4月「奨学金に関するアンケート報告書」より)では、貸与奨学金を受けた若者の4割近くが奨学金返還を「苦しい」と感じているそうです。月々5万円を4年間借り入れた場合、奨学金の借入総額は240万円となります。利子がつくかどうかによっても異なりますが、毎月おおよそ1万4,000円を15年間に渡って返還していくことになります。借入総額が多ければ多いほど、毎月の返還額や返還年月が増えていく仕組みとなっており、中には月に3万円以上を返還している若者もいます。
新社会人で貯蓄もまだ少ない中、給与からそれだけのお金を返還していかなければならないため、大きな負担と感じる人が多いようです。十分な貯蓄ができずに結婚やマイホーム購入をためらうなど、奨学金返還が若者の人生のイベントに大きな影響を与えています。
■学資保険と給付奨学金
子どもが奨学金返還で苦しい思いをしないためにも、親としては貸与奨学金を利用せずに学費を工面したいものです。そのためにチェックしておきたいのが、学資保険と給付奨学金です。
学資保険は、子どもの教育資金を確保するための保険です。毎月保険料を払い込み、定められた満期に給付金として学資金を受け取ることができます。子どもの年齢やライフプランによって保険料や受け取るタイミング(満期)が決められるので、家計や家庭事情に合わせた貯蓄をすることができます。
単なる預貯金と異なるのは、保護者に万が一のことがあった際に保険料の支払いが免除される仕組みがある点と、払い込んだ保険料の一定の金額が所得控除としてその年の所得から差し引かれるため、所得税・住民税の負担軽減になる点です。また、返戻率によっては支払った保険料を上回る額の給付金を受け取ることができるので、お得に教育資金を貯めることができます。
給付奨学金を利用するのも方法の1つです。奨学金には、卒業後に奨学金を受け取った学生本人が返還しなければならない貸与奨学金のほかに、返還不要の給付奨学金があります。
給付奨学金は主に自治体や企業、大学が運用しており、さまざまな種類のものがあります。返還不要な奨学金なだけあって審査は厳しく、奨学金を受けられる人数も多くはありません。しかし受け取ることができれば学費の負担を大きく減らすことができるため、どうしても奨学金が必要な人は、まずは給付奨学金を受け取ることができないか調べてみることをおすすめします。
いかがでしょうか?。貸与奨学金は有利子のものであっても、通常のローンなどと比べると利率が非常に低く、在学中は返還の必要がないなど学生に非常に有利な仕組みとなってはいますが、あくまでも学生自身の「借金」です。できるだけ貸与奨学金に頼らなくても済むように、学資保険などを利用してあらかじめ教育資金の備えをしておくことをおすすめします。
お金に関する不安・お悩みを解決!ファイナンシャル・プランナーへの相談はこちら





