家計
20代の平均貯金額はいくら?

20代だと、マイホームの購入やリタイア生活などの将来像を想像するのはなかなか難しいもの。
とはいえ、
「ほかの人はどれぐらい貯金できているのか」
「平均の貯金額はどれぐらいか」
と気になっている人は多いはずです。
今回は調査からわかった20代の平均貯金額と、20代から貯金をスタートさせる際のポイントをまとめました。
20代の平均貯金額はいくら?
ここでは、「家計の金融行動に関する世論調査(令和2年)」の調査からわかった結果をピックアップしてご紹介します。
家計の金融行動に関する世論調査(令和2年)
金融広報中央委員会が行った調査「家計の金融行動に関する世論調査(令和2年)」によると、20代の単身世帯の平均貯蓄額(現金のほか、保険や株式を含める)は113万円という結果が出ています。ただし、「中央値」は8万円という平均よりも大きく離れた結果に。
中央値とは、数字のデータを小さい順から並べたときに中央に来る数字を指します。
たとえば「1、2、3、4、100」という数字データが並んでいる場合、このデータの中央値は3です。しかし平均値は22となり、中央値と平均値に大きな隔たりがあることがわかります。
これは、極端に大きな数字に平均値が引っ張られてしまうため。
1つの数字が極端に大きければ大きいほど、平均値と中央値が大きく乖離すると考えると良いでしょう。
このようなケースの場合、平均値よりも中央値のほうがより「真ん中」にあるという感覚が強まります。
そのほか、同調査では20代の単身世帯の「貯金・貯蓄を保有していない(0円)」と回答した世帯が43.2%、「100万円未満」と回答した世帯が28.3%いるということもわかっています。
貯金・貯蓄が全くないか、あっても100万円未満という世帯の割合が70%以上という結果になりました。
20代だと所得がまだ低く、貯金するのは難しいのかもしれません。
20代が貯金をする理由、最も多いのは
「ケガや病気のときの備えとして」、「老後資金の一環」など、貯金の理由は人によってさまざま。
家計の金融行動に関する世論調査によると、20代の金融資産保有世帯の貯金理由は以下のような結果となっています。
病気・災害の際の備え
単身世帯で44.7%、2人以上の世帯で57.1%と最も多かったのが「病気・災害の際の備え」です。突然の病気やケガ、災害に対する意識が強く働いていることがわかります。
とくに単身者の場合、ケガや病気で働けなくなると収入に大きなダメージが及びます。そうした事態に備えて貯金をする20代が多いようです。
なお、2人以上の世帯で同率1位となったのが「子供の教育資金」でした。
レジャー・娯楽費
こちらも単身世帯・2人以上の世帯に共通して目立っていた回答です。
単身世帯で34.3%、2人以上の世帯では38.1%とそれぞれ報告されています。
20代は体力・気力ともに充実している年代。レジャーや旅行を楽しみたい気持ちは、やはり強いようです。
老後資金
「貯金は老後資金のため」と回答した割合は単身世帯で33.0%、2人以上の世帯で33.3%という結果に。
老後資金問題や年金問題を受けて、コツコツと貯金をはじめている人も多いことがわかります。
とくに目的はない
「とくに目的はないが、貯金や金融財産があれば安心」という回答です。
単身世帯は39.2%、2人以上の世帯は9.5%となっており、単身世帯でとくに目立っていることがわかります。
住宅の取得・または増改築資金
マイホームの購入やリフォームのため、貯金する人も多いようです。
これはとくに2人以上の世帯で目立った回答で、割合としては23.8%。一方、単身者世帯は7.9%に留まるという結果になりました。
既婚か未婚かで、住宅に対する意識が大きく異なっていることがわかります。
20代はライフイベントに備えて貯金をしておくべき
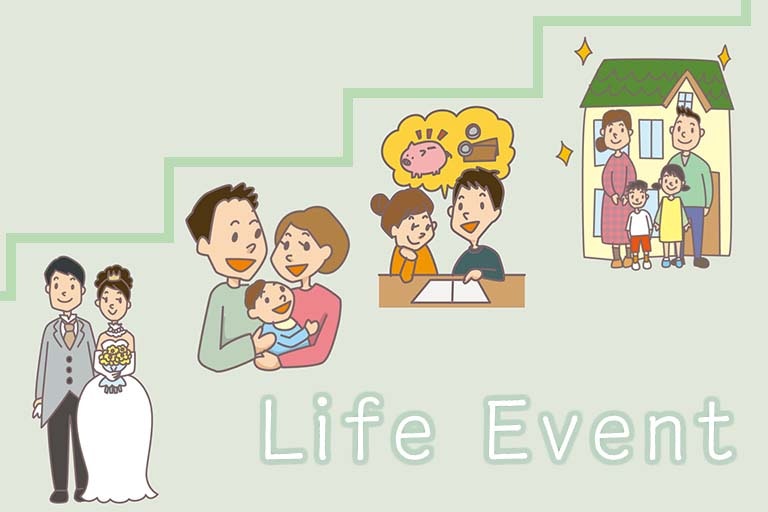
20~30代は、さまざまなライフイベントがある年代です。とくに結婚や出産、子育てやマイホーム購入などは重要なライフイベント。
当然、そのライフイベントに向けた貯金も早いうちにスタートさせておくのがベストです。
以下では結婚をはじめ、主なライフイベント別の平均費用をピックアップしました。
結婚費用
「ゼクシィ結婚トレンド調査2021調べ」によると、挙式や披露宴、パーティーの総額平均費用は292.3万円という結果が出ています。
ご祝儀などを差し引いた挙式や披露宴などの費用の自己負担額は143.7万円という結果に。
結婚式だけでなく、ハネムーンへ行ったり婚約指輪・結婚指輪を購入したりすればさらに費用が上乗せされます。
現在は結婚や挙式の形が多様化しているとはいえ、ある程度は結婚資金を貯めておく必要がありそうです。
妊娠・出産費用
妊娠・出産費用は、妊娠してから出産するまで行われる妊婦健診と実際に赤ちゃんを産むためにかかる分娩や入院などの出産費用になります。ママとママのお腹の中で育っている赤ちゃんの健康状態をチェックする妊婦健診は、病気ではないため健康保険が適用されず、自己負担になります。また、出産するときの分娩・入院費用も病気ではないので健康保険適用外になります。
妊婦健診の費用は、病院やクリニックによって異なりますが、1回の基本健診費用の目安は3,000~7,000円ほどです。特別な検査が必要になると、1万円以上かかる場合があります。厚生労働省が妊婦健診の標準回数としている14回で見積もると、4~10万円ほどかかる計算です。
分娩や入院などの出産費用は「平成28年度の国民健康保険中央会の調査」によると、正常分娩分の平均的な出産費用は505,759円になっています。
ただし、妊婦健診は自治体、出産費用は国から助成金が支給されるため、負担は軽減されます。
とはいえ、妊娠中のウエアや下着などのマタニティ用品や出産後も赤ちゃんを育てるための洋服やオムツ、ミルクなどを揃える必要があるので、多少の蓄えをしておくことが大切です。
教育費
文部科学省の「平成30年度子供の学習費調査」によると、幼稚園から大学卒業までにかかる教育費は1人あたり約1,000~3,000万円と発表されています。国公立か私立か、1人暮らしをさせるか否かで教育費に大きな開きが出ますが、それでも教育費が占める家計のウェイトは大きいといえるでしょう。
ここに習い事や塾の月謝を含めると、さらなる出費になります。
結婚願望があり、なおかつ将来的には子供もほしいと考えているのであれば、20代のうちから少しずつ貯金をはじめるのがベストです。
マイホーム購入費
国土交通省の「令和2年度住宅市場動向調査報告書」では、土地と注文住宅を同時に購入した際の平均費用は4,606万円という結果が報告されています。分譲戸建住宅を購入した場合は平均で3,826万円、分譲マンションは4,639万円という結果に。
これは、あくまでも全国平均で、首都圏や郊外など家を購入する地域によって土地の値段は変わります。
20代のうちは、マイホームの購入といわれてもピンとこないと思います。しかし、家族構成などの変化によっては、家が欲しいと思うときが来るかもしれません。家を購入するときは頭金が必要になることもあるので、将来のマイホーム購入を見据えた貯金を20代のうちから実践しておくことが大切です。
20代から貯金をスタートさせるときのポイント
いくつかのポイントを押さえておくだけで、よりスムーズに貯金ができます。
「今まで何となく貯金をしていた」、「思うように貯まらなかった」という方は、ぜひ以下のポイントをチェックして、それまでのやり方を見直してみてください。
目標を決める
目標やゴールが不明確だと挫折しやすくなります。貯金する目的や意味を見出せず、モチベーションも上がらないからです。
「マイホームの頭金〇〇円を貯める」、「欲しい時計を購入するため○○円が必要」など、明確な目標を決めましょう。貯金する期間を決めておくのも手です。
家計簿をつける
「自分の支出やお金の使い方をきちんと把握していない」という人もいるはずです。そんな人におすすめなのが、家計簿をつけること。
家計簿は、自身の出費傾向やお金の流れを掴むのに欠かせないツールです。家計簿をつけることで使途不明金(何に使ったかわからないお金)や無駄遣いに気づくことができ、節約につながります。既製品の家計簿ノートやアプリなどさまざまな家計簿ツールがあるので、自身に合った記録のつけ方を模索すると良いでしょう。
貯金用口座をつくる
生活費やお給料の振り込み口座とは別に、貯金用口座をつくるのも良いでしょう。普段使いの口座にまとめて入金すると、ついつい残金に手をつけがち。口座を分けることで、そんな使いすぎを防止できます。生活費と別で管理するので、残高記録で混乱することもありません。
先取貯蓄をする
自動積立式の口座をつくれば、決まった金額を自動的に貯金用口座へ入金できるのでとくにおすすめ。余った金額を貯金するのではなく、先取して貯金するという方式にするのがベストです。
「老後資金」、「マイホーム資金」、「レジャー資金」など、目的別の自動積立口座を複数開設するのも良いでしょう。
また、企業によっては各種の財形貯蓄制度があることも。財形貯蓄制度とは、給与から天引きされたお金が自動的に貯まっていく貯蓄制度のことです。
財形貯蓄制度が導入されていないのであれば、iDeCo(イデコ)を活用するのも手。iDeCoは個人型確定拠出年金の通称で、個人で任意加入できる年金制度を指します。
自身で掛け金を拠出し、任意の運用方法で掛け金を運用。最終的に、運用益と掛け金を合算した金額を受け取れるのが特徴です。
60歳未満の現役世代であれば誰でも加入でき、運用できるのもポイント。先取貯蓄の一環として、加入を検討するのも良いでしょう。
ただし、財形貯蓄は基本的にいつでも引き出すことができますが、iDeCoは原則60歳まで引き出せません。
リタイア後の生活を少しでも豊かにするために、20代の早い時期からiDeCoを始めてはいかがでしょう。
お金を分類する
お金をひとまとめにせず、分類して管理しましょう。
具体的には、「使うお金」「貯めるお金」「増やすお金」に分類します。
まず「使うお金」は、生活費として普通預金口座で管理するお金です。
この口座には、「いざというときにいつでも使えるお金」を入れておきます。
「貯めるお金」は、マイホーム資金や結婚費用、子供の教育費用など目的や目標額を決めたうえで貯金するお金です。
専用の自動積立口座などで管理しましょう。
「増やすお金」は、上記の項目から余ったお金です。
もし余剰金が手元に残るのであれば、資産運用に使うお金として別で管理すると、将来のための貯蓄にもつながります。
高額な固定費を見直す
毎月何となく固定費を払い続けている人は、固定費を見直す癖をつけましょう。日々小さな節約を重ねるよりも、高額な固定費を見直すほうが貯金効果は大きくなるのです。
たとえば、大手キャリアのスマホを格安スマホへ変えるだけでも、毎月の出費を大きく削れます。
使用頻度が低い定額サービスを解約したり、電力会社のプランを見直したりするのも効果的です。
もし可能であれば保険会社のプランを見直したり、家賃節約のために思い切って引っ越したりする手もあります。
固定費だけでなく変動費の見直しも
大きな固定費だけでなく、毎月の変動費もしっかり見直しましょう。美容代や趣味のお金、交際費などの変動費は「おこづかい」と捉えます。
おこづかいの理想は支出全体の10%程度とされており、オーバーしているのであれば要注意です。
家計簿をつけてお金の流れを把握するのはもちろん、レシートや明細を見て「役に立ったアイテム」、「買わなくても良かったアイテム」を記録していくのがおすすめ。
たとえば「重宝している調理器具」なら◎、「使い心地が良くないコスメ」は×というように記録します。
自分が買い物で失敗する傾向が明確になり、節約の糸口が見えてくるでしょう。
貯金する金額の目安
毎月の貯金額は、手取り給与の10~20%が理想。手取り給与の10%を貯金することが難しいのであれば、生活スタイルや支出を改めて見直すことが重要です。
貯金しようと強く意気込むあまり、収入に見合わない金額を貯金するのは避けましょう。とくに、心身の健康を損ねてまで貯金をするのは本末転倒。まずは出費の傾向を把握したうえで、無理のない範囲で貯金をスタートすることが重要です。
貯金・家計管理で迷ったらFPへ相談
自己流で貯金を始めても、なかなかうまくいかず悩む人は少なくないはず。そんなときこそ、お金や家計管理のプロであるファイナンシャル・プランナー(FP)に相談してみるのがおすすめです。
ニッセンライフのFPナビでは、家計相談をはじめ結婚・子育て・老後などのライフプランの相談などさまざまな分野に対応。
何度でも無料でご利用できるため、安心してご相談いただけます。相談場所はFP事務所をはじめ、ご自宅やカフェでもOK。
家計相談の分野では、FPがプロの目線から家計の問題点を分析。そのうえで、収入やライフプランに合った節約・貯蓄方法をアドバイスさせていただきます。
ぜひご相談ください。
※この記事は2021年10月時点の法律・情報に基づき作成しているため、将来、法律・情報・税制等が変更される可能性があります。
出典
「家計の金融行動に関する世論調査[単身世帯調査](令和2年)」(金融広報中央委員会)
https://www.shiruporuto.jp/public/data/survey/yoron/tanshin/2020/20bunruit001.html
「家計の金融行動に関する世論調査[二人以上世帯調査](令和2年)」(金融広報中央委員会)
https://www.shiruporuto.jp/public/data/survey/yoron/futari/2020/20bunruif001.html
「ゼクシィ結婚トレンド調査2021調べ」(株式会社リクルート)
https://souken.zexy.net/data/trend2021/XY_MT21_release.pdf
「出産費用 平成28年度」(公益社団法人 国民健康保険中央会)
https://www.kokuho.or.jp/statistics/birth/2017-0620.html
「平成30年度子供の学習費調査の結果について」(文部科学省)
https://www.mext.go.jp/content/20191212-mxt_chousa01-000003123_01.pdf
「私立大学等の平成30年度入学者に係る学生納付金等調査結果について」(文部科学省)
https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/shinkou/07021403/1412031_00001.htm
「令和2年度住宅市場動向調査報告書」(国土交通省 住宅局)
https://www.mlit.go.jp/common/001401319.pdf





